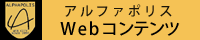レオン・クミン記
ミッド大公ハーン家祐筆 レオン・クミンによる回述
二重の喜びだった。
己の話に、興味を持ってくれる人物がいたこと。
そしてその人物が、その女性であったこと。
「姫若様へ語る、お伽噺のネタ仕入れですか?」
試みに、問うてみた。
その女性……クレール=ハーン姫付き侍女、教育係にして学友……ガイア・ファデッド嬢は、気恥ずかしそうに微笑んで、首を横に振った。
「純粋に自身の興味から、ですよ、クミン殿」
輝いていた。
近衛兵の着る真紅のジャケットを羽織り、折り目正しいプリーツがゆったりと重なった濃紫の丈長なキュロットをはいたその姿も、日に灼けた頬に浮かぶ凛々しい微笑も、全てが我が目に眩しかった。
ここは、何事も控えめ……地味ともいうが……な我が故郷ミッド公国で、唯一「壮麗なサロン」と呼んでもよい場所だ。
とはいうものの。
確かに、貴族達、金持ち達が主な客だが、普通の臣民も慶事には多々利用するから、他の「大国」から見れば、単なる「レストラン」に過ぎぬだろう。
しかし、私は嬉しかった。
ここにファデッド嬢と向かい合って居、共に食事を摂っていること、それ自体が至福だった。
「……クミン殿?」
ファデット嬢が、私の目を覗き込み、不安げな声を出した。
「聞いて、おられるか?」
「無論!」
私は精一杯の笑顔を浮かべた。
きっと、普段は青白い頬が、炎のように赤くなっていたに違いない。
「私は、嬉しいのですよ、ファデッド嬢。私は……」
「クミン殿、嬢は、止めていただきたい」
ファデッド嬢は、照れた笑みを浮かべ、掌を大きく左右に振った。
「そのようには、呼ばれ馴れていないのですよ。それに、私は貴殿より年下、それに爵位も……。ですから、ガイアと呼び捨ててくださって結構」
息を呑んだ。半信半疑とはこのことだ。
こんな光栄なことが、我が身に起こって良いのだろうか?
呼び捨ててよい? それも、ファーストネームで!?
私は、持てる勇気の全てを振り絞って、それでも恐る恐る言った。
「で……では、ガイア……」
「はい」
ファデッド嬢……いや、ガイアは、満面の笑みでうなずいてくれた。
私は一瞬、気を失うのではないかと思った。
笑わないでいただきたい。私には、それほどに幸福な瞬間だったのだ。
私は深呼吸を一つすると、努めて冷静に、ガイアに訊ねた。
「何からお話しすれば良いのでしょう?」
ガイアは、わずかに小首を捻った後、ゆっくりとした口調で答えた。
「最初から。そう、今日の昼下がり、お茶の時間に、貴殿が姫若様と私とに語ってくれた話から。そして叶うことなら、貴殿がその時語ってくれなかったことを、全て」

そう。
この日の昼下がり、私は、クラウンプリンセス・クレール姫の三時のお茶のご相伴に預かる幸運を得た。
予定されていた大公ジオ三世殿下ご臨席の会議が、司空(建設大臣)殿の急な病で中止となり、時間が空いたのが……司空殿には気の毒ではあるが……幸いしたのだ。
ご利発で、何事にも興味を示される、少々御転婆なクレール姫は、親友とも呼んでよいであろう学友であるガイアと、二人きりで歓談するおやつの時間に、このところ少々飽きておられたらしい。
強く男子を欲しておられていた大公殿下は、この姫君を若君の如くお育てになられた。
これをして、「姫のような若君だ」などと事実に反することを言い、「姫若」などと呼ばわる愚か者がいた。どちらかといえば「若のような姫君」であるから「若姫」が正当であろうが、当のクレール姫は何故か前者の呼ばれ方をお気に召しておられるようだ。
それは兎も角も。
ありきたりの少女であれば甘い菓子とお茶だけで数時間は時を過ごすことができるにもかかわらず、姫はそういった穏やかな時間の使い方が苦手であられる。
姫若様はいつも彼女に、「お話」をせがまれる。
それも毎日違う物語を、だ。
しかし、いくら博学とはいうものの、まだ年若いガイア……実はまだ十五歳で、姫若様とは五つほどしか違わないのだ……が知る「うわさ話」「お伽噺」「昔話」「寓話」「冒険譚」には限りがある。
新しい話題を求められる姫若様の哀願に、彼女が困り果てて辺りを見回した、丁度その視線の中に、暇を得た私の姿が映ったのだ。
運が良かった。……ガイアにとっても、私にとっても……。
小さな国の主の城、というか領主の屋敷というか……の、猫の額ほどの美しい中庭に設けられた、小さな丸テーブルでのささやかなお茶会だった。
「とても不思議なお話です。……少々恐いお話になるかも知れませんが、それでもよろしいでしょうか?」
私は精一杯の笑みを向けた。
正直な話だが、私は笑うのが少々苦手なのだ。
いや、自分では笑っているつもりなのだが、生来の顔色の悪さが、「つもり」を他人には知らせてくれないようなのだ。
しかし今回は巧く笑顔を作れたらしい。
クレール姫様は、嬉しそうに大きくうなずかれた。
「恐いお話は大好き。ねぇ、ガイア?」
同意を求められたガイアは、少し困惑気味ではあったが、首を縦に振った。
「解りました。……では、恐くてもう聞きたくないと思われたら『もう止めなさい!』と、ご命令下さい」
そう前置きして、私はこんな「物語」を語った。

男の子が居りました。小さな男の子です。
体が弱く、よく病気をしていたので、ずっと長いことある病院に入院していました。
ある天気の良い日、男の子は同じ部屋で眠っている、お年寄りの病人の頭の上に、何かが乗っているのに気が付きました。
それはまるで、高い山のてっぺんに懸かる、丸い雲のような物でした。
雷雲のように少し黒みがかったそれは、お年寄りが起きても、食事をしても、お手洗いに立っても、そしてまたベッドに戻っても、ずっと頭の上に乗り続けています。
初め男の子は、自分の目がおかしくなったのだと思いました。
少し前に、ぼんやり目が霞む病気にも罹ったことがあったので、またその病気が顔を出したのだと、そう考えたのです。
その晩のことです。
真夜中、そのお年寄りが急に苦しみ始めました。
お医者さまは慌てて飛び起きて、一生懸命介抱しましたが……とうとう、お年寄りは助かりませんでした。
次の日の朝のことです。
男の子は、隣の病室に入院している小さな女の子の怪我人が、病院の庭で日向ぼっこをしているのを見かけました。
そして、その女の子の頭の上に、何かが乗っているのに気が付きました。
それはまるで、高い山のてっぺんに懸かる、丸い雲のような物でした。
秋の鰯雲のように真っ白なそれは、女の子が歩いても、絵本を読んでも、看護婦さんとお話をしていても、ずっと頭の上に乗り続けています。
夜が来て、朝が来て、お昼が過ぎました。
男の子がベッドの上で横になっていると、隣の病室から、泣き声が小さく聞こえてきました。
怪我をして入院をしていた、小さな女の子の、お母さんの泣き声です。
「ああ、娘よ。たった一人の娘よ! なんでお母さんよりも先に死んでしまったの!?」
少し前に手術をし、しっかりと縫い合わせた、そしてもうじきふさがるはずだった傷口が、何かの拍子にパックリと開いて、急に血がたくさん出てしまい、それが元で、あの小さな女の子は死んでしまったのです。
夜が来て、また朝が来ました。
病院のドアを叩く大きな音で、みんなが目を覚ましました。
「急患です、急患です! 先生、人足が荷車の下敷きになりました! お願いです、診てください!」
男の子は病室のドアを少しだけ開け、その隙間から、病院の入り口の方をのぞき見ました。
戸板の上に乗せられた、血まみれの男の人は、どんよりとした真っ黒な雲に包まれています。
お医者さまが、力無く首をふりました。
「もう手遅れです」
男の人の仲間や友達や家族が、わぁわぁと泣き出しました。
男の子はドアを閉め、自分のベッドに飛び込みました。
実は、もう一つ雲が見えていたのです。
あの血まみれの男の人を包んでいたのとは違う雲です。
それは、男の人の家族……たぶん、奥さんか恋人でしょう……の頭の上に乗っていました。
白い雲でした。輝くような白い雲でした。
……数日後、男の子はうわさ話を聞きました。
「博打とお酒と喧嘩が大好きで、悪いことをたくさんしたことのある荷揚げ人足のことを、それでも大好きだった優しい娘さんが、その人足が事故で死んだのがショックで、病気になって死んでしまった」
男の子は恐くなりました。
身体が、ガタガタと震えました。
「僕が頭の上に『雲』を見た人は、全員死んでしまった!」
一日中、毛布を頭までかぶり、ご飯も食べないで、泣いていました。
それでも、しばらく後には、男の子の病気はだいぶ良くなり、退院することになりました。
男の子は下を向いたまま病室を出、下を向いたまま廊下を歩き、下を向いたままお医者様に挨拶をし、下を向いたまま外に出ました。
見えるのです。
何人かの患者さんの頭の上に、黒っぽいのや白っぽい雲が漂っているのが。
見えるのです。
外を歩く人々の中にも、黒っぽいのや白っぽい雲を、頭上にたなびかせている人達が何人も。
見えるのです。
親戚の人や、おうちの近所の人や、知っている人達の中にも、黒っぽいのや白っぽい雲を担いでいる人のいるのが。
そうして、そんな人達が全て、しばらくたつと死んでしまうのです。
「死神だ」
男の子は思いました。
「僕には死神が見えるのだ」
男の子は、一生懸命「雲が見えること」と、「雲が見えた人はもうじき死んでしまうのだ」ということに馴れようとしました。
何年もかかって、ようやく馴れることはできました。
しかし、馴れてからは、もっと辛くなりました。
大好きな人、大切な人、尊敬する人、そんな人達の頭の上に雲が乗っていても、その雲を追い払うことができないからです。
忠告することはできます。
ですが、誰も信用してくれません。
信じてくれたとしても、その雲が消えることはありませんでした。
我慢するしかないのです。
例え、あなたの頭に雲がかかっているのが見えたとしても……。

私は最後の一言を言いながら、クレール姫様の頭の上あたりを指さした。
と。
「きゃぁー!」
日ごろお勇ましい姫若様が頭を抱え、テーブルに突っ伏し、ブルブルと震えながら、
「見えるの? 私の頭に、雲があるの!?」
と、エメラルドの目から大粒の涙をこぼされたのだ。
「見えません」
私は答えた。できる限り、優しい顔をしたつもりだった。
姫若様は、そぉっと顔を上げ、私を睨み付けると、
「真面目なレオンがこんなに不気味で恐ろしい話をするなんて、思っても見なかった。でも、とても面白かったから、許します」
涙を拭いながら、にっこり笑い、お褒め下さった。
その時、ガイアは苦笑いをしていた。
楽しそうな、苦笑いだった。
「あの物語、実は『作り話』ではないのでしょう?」
食前酒のグラスを揺らしながら、ガイアが私を見つめた。
「あれは貴殿自身の身に起こる事象。実際に貴殿には……『死神』が見える……違いますか?」
真剣な眼差しだった。
私は、うなずいた。
「貴女に信じていただけるとは、思ってもいませんでした。何分、貴女というヒトは、頭が良い上に、実力主義・現実主義な方だと思っておりましたから」
「貴殿にそう評して頂けたことは、実に喜ばしい。……事実、私は実力主義・現実主義を信条にしています。……だからこそ、貴殿の『能力』に興味がある」
「『能力』……と言われるか? この不可思議な現象を?」
ガイアは真剣な瞳で、しかし、口元には笑みを浮かべて、こう言った。
「目が見える。匂いを嗅げる。耳が聞こえる。味を感じる。物に触れる。あるいは、喋る、歩く、走る。……誰しも当たり前に取る行動だ。しかし、盲目の者にとっては、見るということ自体が『特殊な能力』に思えることでしょう。嗅覚をなくした者には、薔薇の香りをかぐこと自体が『己には感じ得ない感覚』となりましょう。聾唖の者、身体が麻痺した者、四肢を失った者には、音も、触感も、歩くことも、『自分にはできない能力』となる……違いましょうか?」
私は驚いていた。
細い目を見開き、口をポカンと開けた、相当にしまりのない顔をしていたことだろう。
本当に、私は驚いていた。
ガイア・ファデッドという女性の聡明さに、その英智の深さに。
そして、自身の感情に呆れていた。
この、世間から「男女」だの「おんな女形」などと呼ばれる女性に、一目会ったその日から恋心を抱いた、己の洞察力の深さに。

それにしても、私はガイアに対して負い目を感じていた。……体格、体力面でのことだ。
何とか背丈だけは勝っている。
とはいえ、私はひょろ長いだけのホワイトアスパラのごとき体躯である。彼女と並び歩くと、他人から蚤の夫婦となどと揶揄された。
……この噂が自身の耳に入った時点で、私たちの密やかなつもりであった仲が、公然であることの不自然に気づけばよいものを……。
さておき。
文武百官が居並ぶ場では、私の惨めさはことさらに極まる。
文官の列に私がいるのが「当たり前」であるように、武官の列には「当たり前」のようにガイアがいた。
一介の公女付き女官が、そのような席に立つことは、過去にないことであるし、おそらく今後もないであろう。
しかし、ガイア・ファデッドは特別だった。「護姫将軍」という雑号官を新設させるほどの武芸者なのだ。
特殊な武官として列席する彼女の一つ上座が、近衛隊長のデュカリオン卿である。
たくましい美丈夫と並ぶ彼女。
似合いなのだ、二人は。
私が彼女と並んだとて、あれほどしっくりと「絵」にはなるまい。
私は嫉妬した。怯えていたと言ってもよいだろう。
そして情けないことに、いつしか私は、デュカリオン卿を勝手に仮想敵(ライバル)と見るようになっていた。
卿に負けるまいと、小さな虚勢を張るようになったのだ。
例えば。
私はそれ以前、佩剣を正装の一部としか思っていなかった。
それも、フック一つで結ぶ手間なくつけられる蝶タイと同程度の、である。
だから私の腰には、レイピアの柄と鞘しか下がっていなかった。
本身を持つ必然性は、私の中には無かった。わざわざボウタイを美しく結わえる必要がないように。
その柄に、ある日突然刃を付ける気になった。
仮想敵に対する備えだ。……腕力を持って争ったとして、私が勝てるはずは万に一つもないと言うことを、重々承知した上での、蟷螂の鎌である。
クミン家は、伝統ある名家である。父祖より伝来する無銘の名刀が、使われることなく納戸の奥で埃に埋もれていた。
それを柄にすえ、帯びた。
黒光りする真鉄が、華奢な私の腰を大地に引き寄せようとする。
帯剣したまま歩くことができないという事実に、私自身が驚愕した。
そして。
ガイアが帯びているのが、レイピアなどよりも数倍重い、ロング・バスタードであることを思うと、彼女への尊敬の念はさらに深まった。
日々は過ぎ、何とか剣を携えたまま歩けるようになった頃、私は毎夜、夢を見るようになった。
ガイアの髪は漆黒なのだが、陽の光の元では緑に輝く。
ガイアの瞳は琥珀色なのだが、時として青みがかる。
風吹く草原のただ中、ガイアの髪は揺れ、ガイアの瞳はきらめく。
私はそれを眺めている。
ただそれだけの夢を、毎夜見る。
そのころから、私の様相は、激変したようだ。
落ちくぼんでいた黒い瞳に光が射したようだと、幕僚の一人が言った。
痩けていた頬に赤みが差したと、部下が言った。
皆、私の心中を察しあぐねている。
あてがわれた執務室と自宅とを往復するばかりだった日常が、それに何の不服もなかった日々が、酷くつらく感じられた。
息をするのもつらい。思考するのも苦しい。
ただ一つの想いだけが、私の心を占拠している。
この様に苦しい日々は、それまでの人生二十年の内にはなかった。
あの人のこと以外は考えられない。
毎夜、夢を見た。
それが夢であることが悲しかった。
それを現にしたいと願った。
決心するのに半年かかったが、たった半日で実行に移した。
まず私は、私はプロポーズの言葉を考えた。
はじめの内は、浮かび上がってくる言葉が、あまりに陳腐であったので、我が脳漿の不出来に幻滅したものだ。
しかし、悩む内に良いアイディアが浮かんだ。
なにも、己の気持ちを言葉で飾り立てずも良いではないか。
その気持ちそのものを、彼女に伝えれば良いのだ。
鈴蘭の月、聖・ガイアの日……彼女の誕生日は明日に迫っている。(彼女は誕生日の聖人の名をそのままつけられたのだ)。
日の明ける前に、普段から誰よりも早く登城するガイアよりも前に、彼女の執務室に入り、彼女を待つ。彼女がドアを開け、彼女の椅子に坐る私を見つけて驚く。そこで、求婚する……祖母の形見である、赤珊瑚の指輪を婚約指輪として差し出しつつ……。
そんな算段だった。
常夜灯の明かりもかすかな屋形の中を、私はそっと進んだ。胸を張って、堂々と、しかし静かに。
自分の気持ちの高ぶりを、何とか押さえ込んで、部屋の前に立つ。
ドアノブを握る。
押す。
直後、私の体はガイアの執務室の中に、吸い込まれていた。
私自身は何の力も使っていない。
ドアが内側から開いたのだ。
「うわぁ」
情けない悲鳴を上げたつつ、私は『ガイアが私の想像より早く出仕していた』と思い、倒れ込みながらそこにいるであろう彼女の姿を捜した。
だから、男物の、品は良いがかなりくたびれたブーツが視野に入ったときは、酷く驚いた。
それが見慣れた黒革であったから、なおさらだった。
私が
「陛下!?」
と叫んだ直後、顔面は床に叩き付けられた。
ミッド大公ジオ=エル・ハーン三世“陛下”と、クリームヒルデ妃、そして三名のお針子達が、狭い部屋の中に居た。
両陛下はもちろん、お針子達も私のよく見知った顔だった。
国一番の裁縫の匠で、いつもクリームヒルデ妃やクレール姫のドレスを仕立てている者達である。
皆が「何が起きたのか判らない」という顔をしていた。私も同じだった。
立ち上がり、両陛下の御顔を見比べ、さらにお針子達の手元を見、
「ガイア・ファテッドへの今年の誕生祝いは、一級品のドレスでございますか?」
できうる限り平静を装い、落ち着き払ったつもりの声と顔で、私は尋ねた。
お針子の一人イフィゲニアがスケールを持っており、オレステスがデザイン帳を、エレクトラが布地の見本帳を持っているのを見れば、夕食のメニューを相談しているのではなさそうなことぐらいは判る。
「考え方は、良い。だが、ドレスそのものは、誕生祝いの贈り物ではない」
ジオ三世陛下が照れ隠しのような咳払いをなされた。するとクリームヒルデ妃が続けて、
「誕生日当日に贈り物のドレスの採寸をするほど、あたくしどもものんびり屋ではありません。今日採寸してドレス本体を縫い上げるのに一ヶ月半ほど、レースや装飾をほどこすのにもう一ヶ月半はかかるのですよ」
「都合三ヶ月、にございますか?」
私は、向こう三ヶ月の公国の公式行事スケジュールを、頭の中で検索した。
ガイアがドレスを着なければならない「行事」の予定は、三ヶ月の内には思い当たらなかった。
確かに、四ヶ月後に両陛下の二十回目の結婚記念日兼ミッド公国建国記念日がある。
その半月先にはクリームヒルデ妃の、さらに七日間後にはジオ三世陛下のご生誕日、クレール姫のお誕生日はそのさらに一ヶ月ほど先。
お三方の誕生祝いは、ご成婚記念と併せて、まとめて建国記念日に行うのが通例となっている。(五度のパーティーを一度にすれば、経費を五分の一に押さえられる、とジオ三世陛下が発案なされたのだ)
「どうした? 日頃の切れ者ぶりが、最近は薄らいでおるな」
陛下が含み笑いをなさった。
私は首を傾げざるを得なかった。
「その方の、誕生日があるではないか」
確かにその通りではある。
「その方の父セインが、その日取りを提案したのだぞ」
唐突に父の名を聞き、私は困惑を深めた。
陛下は続けて、
「ガイアの父ニクスも、それを承知して……」
と、言いかけ、あわてて口を塞いだ。
クリームヒルデ妃が、夫の耳元で
「そのことは、直前まで内緒の約束です」
とささやくのが、漏れ聞こえた。
『そのこと』が何を指すのか、瞬時には判りかねた。
そのとき、お針子のオレステスが、デザイン帳の一葉を開き、こちらに示した。
描かれていたのは、古風でシックなドレスだった。
しかし、長く尾を引くようなレースのベールや、裾を飾る刺繍、胸を飾るビーズは、本当にこの絵図通りに仕上がるのなら、このドレスが途轍もなく豪華な物になることを暗示している。
使われている色は、白ただ一色。
私が息をのんだと同時に、背後で物音がした。
振り向くと、ガイアが立っていた。
足下に、書類が散乱していた。
私とガイアとが知らないところで、ジオ三世陛下を含めた「親の世代」達が、企んでいたのだ。
ガイア・ファデッドをレオン・クミンの妻に、レオン・クミンをガイア・ファデッドの夫にすることを。
すべてを国費でまかなう荘厳な結婚式の企画というとんでもない代物を、誕生祝いとして受け取ったガイアは、声もなく立ちつくした。
そして、すべてを国費でまかなう荘厳な結婚式というとんでもない代物を、誕生祝いとして受け取ることになる私の胸の中に、気を失って倒れ込んだ。

不幸は、唐突で早足だ。
「我が主は、返使者にはクミン卿を是非に、と」
ユミル女王国からの使者が、こわばった顔に笑顔を浮かべた。
ジオ三世「陛下」の誕生祝いには、ギュネイの全土から祝いの品が届く。
七の自治州、十二の公国、そしてギュネイ皇帝フェンリル陛下以下諸侯からも。
我が国からの返礼は、特産の絹織物である。
実は、情けなくも悲しくも、ミッドには絹縞以外に産物がないのだ。
山に囲まれた狭い盆地の国である。耕作も牧畜もままならない。
唯一育つのが桑であり、唯一養えるのが繭蛾なのである。
それゆえ、養蚕の匠、糸取りの匠、機織りの匠、染色の匠、刺繍の匠、みなが競って技術を高めている。
こうして、同重量の金と同じ値で売買されるほど高品質な産物となった絹綾であるから、毎年決まって絹一反の進物、であっても、諸侯から殺到するのは、苦情ではなく礼状なのである。
さて。
ユミル女王国は島国である。
ガイア大陸より海溝を挟んで東南の地に在する火山性の諸島で、国土は全島合わせて我が国と同じという、小国であった。
しかし、経済では我が国よりも格段に裕福である。
その狭い国土に各種鉱石を孕んでいるからだ。
金、銀、および水銀、あるいは、水晶、翡翠、まれに金剛石をも産する、他に類を見ない土地であった。
ギュネイ帝室も、そのためこの小国を屈服させかね、一応は「属国」としてはいるものの、内政には全く干渉できないでいる。
現君主ギネビア女王は、わずか七歳で即位されて以来十余年、良臣に傅(かしず)かれて善政を敷いておられた。
そのギネビア女王に、なぜか私は好かれているらしい。
四年ほど前に、女王の父君の葬儀の折、我が国から赴いた弔問使節の一員に、私が含まれていたのが発端だったと思われる。
そのとき特に何をした、何があった、という記憶は(少なくとも私自身には)ないのだが、どういった訳か、それ以来、
「我が国へ使者をお立ての場合は、必ずクミン卿にしていただきたい」
ということになっている。
夕刻。
私とガイアは肩を並べて帰途を進んだ。
互いに忙しい身である。
悲しいかな、登城の行き来の道すがらぐらいしか、共に語り合う時間がない。
しかしこの日、ガイアは不機嫌だった。
元から多弁ではないが、この日はとくに無口で、笑顔を浮かべることもなかった。
いや、前日の夕刻から少々口数が少なくはなっていた……ユミル女王国からの使者が、翌朝謁見するというのを知っていたからだ。
明けて朝から、ガイアは自発的な発言をまるきりしてくれなかった。
私にとって不満だったのは、クレール姫とは会話をしている、という事実である。
まぁ、それが彼女の仕事ではあるのだが。
さておき。
夕方になると、彼女はいっそう無口になっていた。
朝は、それでも生返事の受け答えぐらいはしてくれたのだ。
それが、口を真一文字に結び、まっすぐと前を見(つまり、私に眼差しを注いでくれることが全く無く)、家路を急いでいる。
道行きは、ほんの小半時。途中で右と左に分かれ進むことになる。
この沈黙の理由は、良く判っている。
ユミルの使者だ。ユミル女王ギネビア様が、遠因なのである。
私が女王に好かれている理由を、ガイアはかねがね不審がっていた。
私の許嫁に「嫉妬心」などという俗な感情があるとは信じがたいが、女王が評判の美女であり、また、評判通りの美女であることを鑑みれば、不安になるのも致し方があるまい。
ありきたりの娘連であるなら、金切り声をあげて泣き叫ぶのだろう。
そうなると、男の方は責が無くとも取りあえず謝って、アクセサリーの一つも送って機嫌をとるらしい。
それで済むなら、その方が楽と言うものだ。
ガイアと私の間に限って言うと、そういう解決法は成立しない。
「不可解」
ガイアが、ぴたりと足を止め、一言漏らした。
四つ辻が、遠く見える。
まっすぐ進むと国境の関。
右に折れると、ハーン帝国来の旧臣達の住まう地区に行く。私の荒屋はそちらにある。
左の方には、ミッドに古くから住まう豪族達の屋敷が点在している郡がある。ガイアの生家は、その中でも有数の名家だ。
「何が、ですか?」
私も、公道の真ん中で立ち止まり、訊いた。
道の脇に、大きな石がある。ガイアが、視線を持って私をそちらに促した。
ディベートが開始される。
私たちの間でなにか不振ごとがあったときの、唯一の解決法が、これなのだ。
納得できないことは納得するまで追求する、非常にやっかいな性質を、私もそしてガイアも備えている。
これが、他人の目には奇妙に映るという。
普段から、「互いの意見を交換し、検証し、熟考しながら検討し、発表交換し、検証し……を、解決を見るまで繰り返す」会話を、当たり前にしている私たちとしてみると、欲とごまかしで成立するプレゼントなどで問題を解決する方が、疑問なのだが。
驚くべきことに、私たちのディベート、そして日常会話までもが、私たち以外の者には口論に見えるというのだ。
デュカリオン卿に至っては、
「毎日ケンカをしているようだが、大丈夫か?」
と案じてくれるほどだ。
どうも私たちは常識から逸脱しているらしい。ただ論理的であるだけなのだが……。
兎も角、今ガイアが一番納得できないことは、くだんのギネビア女王のことであろうから、それについて、解決に至る理由と意見と検証を求めているに違いない。
しかし、私自身にも理由が判らないことであるから、判らないと説明するより他にないのだ。当然、それで理解が得られるとは思っていない。
私は、今まで幾度かユミルに行き来した折りの出来事を、できるだけ細かく思い出そうとした。
確かにそれは、彼女の「不可解」に関係のある考察ではあった。
だが、的確ではなかったようだ。
ガイアの問いは、この様に続いた。
「……ギネビア女王はかつて、陛下の誕生祝いに、わざわざ返礼を求められたことがあっただろうか?」
私は、脳漿内で行っていた記憶の検索の方向を、瞬時に、そしてわずかに、変更した。
ユミル女王国と、我がミッド公国との交流は、十五年に及ぶ。すなわち、ジオ三世陛下がこの地に封じられて以来の友好国だ。
もとより、火山国ということ、また「孤島」と「陸の孤島」であることの点で互いに共感し、第一次産業を発展させられないという切実な共通問題もあって、二国は友情にも似た国家関係を結んでいた。
その長き年月の中で、王国側から何かを求められ、あまつさえそれをミッド側の者の手で、運んだことがあったろうか?
「そのようなことが、あった例がありません」
私は、瞑目したまま、きっぱりと言った。
「こちらから礼の品を差し出しても、三度は断るほど奥ゆかしい国柄。あちらから何か請求されたことがあると言えば……大公妃殿下のネックレスの代金ぐらいです」
「ではなぜこの度は、わざわざ『返礼の使者』の指名をしたか? ……不可解ではありませぬか?」
彼女の問いに、私はすぐには答えなかった。
どれくらい黙っていたのか、客観視できないため判らない。
私はほんの一瞬息を呑んだ程度だと思っていたが、後々ガイアから「息が詰まって気を失ったのではないか、と気を揉んだ」と聞かされたから、実際は相当長く沈黙していたらしい。
私はあらゆる可能性を考慮した後、
「……『返礼を持って使者が来る』ではなく『返礼を口実に使者がやって来る』ことが必要な事態が起きた……と、考えてみましょうか」
という提起をしてみた。
「返礼を持ってくる使者として不自然でない人間、かつ、問題を解決……ないし有効な助言の提起が……できる人材、か。……レオン・クミン卿しか考えられない」
ガイアは、誇らしげな、しかしすばらしく寂しそうな、そして拗ねて怒ったような顔で答えた。
ユミル女王国に行くためには、陸行すること四十五日、水行すること三日を要する。
つまり、往復するだけでゆうに二ヶ月かかることになる。
しかも、幾日滞在すればよいのか、今のところ見当が付かないのだ。
私とガイアとの結婚式は、残念ながら延期せざるを得ない状況となった。
私たちは諦めることが……表面的には……容易にできた。
親たち、そして大公「陛下」および妃殿下の説得も、国の大事という言葉で押し切った。
残る難点は、2つである。
臣民の中には、私たちの結婚式から建国記念日までのおおよそ一月、さらにはクレール姫の御誕生日まで含めた4ヶ月間そのものを、長い長い祭りとして楽しむつもりでいる者達が多くいた。
そういった人々にとっては、前夜祭に等しい私たちの結婚式が順延されるのが、ひどく残念だったようだ。
私の家にも、ガイアの屋敷にも、そしてあろう事か大公宮にまでも、幾人かの者達が詰めかけて、家人たちを困惑させた。
大公宮の門兵が、彼らを帰宅させるための「丁重な言い訳の仕方」を考えて欲しい、と切羽詰まった顔で訊くので、仕方なく
「前夜祭が後夜祭に変更されただけだ」
と言うように指示をした。
それが功を奏したのか、臣民達の間の騒ぎは次第に収まっていったのだが……。
「敵前逃亡ではありませんか!」
クレール姫がガイアを捕まえてそう仰ったのは、私がユミル女王へ出立する前日の午後、恒例のお茶の時間のことであった。
この場合、敵はガイア(あるいは結婚式)で、逃亡したのが私、ということだろう。
「恋人や妻より仕事を優先させるような男と、ガイアは結婚すべきではありません。ガイアの夫たるべきは、ガイアが多忙なのを助け、ガイアを慈しみ、包み込むように愛する人。常にガイアの傍らにいて、ガイアの支えになってくれる殿方でないといけないのです」
私は、中庭に面する通路の柱の陰で、私は苦笑いしていた。
姫の言葉の中の「ガイア」はすべて「クレール」に置き換えねばならない。すなわち、そのような男性を、姫はお好みであられるのだ。
男児を欲しておられた大公殿下の意向で、男の子がするような厳しさで剣術や学問を学ばれた姫若様が男性に求める「理想」は、すこぶる高い。
姫若様は続けて、
「私がガイアのヴェールを持つことになっていたのに。ブーケだって、私が貰うことになっているというのに!」
いかにも少女らしいお言葉だった。これもまた、ご本心であられよう。
拗ねて、愛らしい下唇を突き出した姫に、ガイアは
「ノルナ姉妹の工房へご同行願えませぬか?」
と、促した。
ノルナ姉妹……つまりお針子のイフィゲニア、オレステス、エレクトラ……の縫製工房は大公宮後門の外側にある。
公室のお召し物を一手に引き受ける名工とはいえ、公人の仕事は実は少ない。
もとより奢侈(ぜいたく)を嫌われるお家柄ゆえ、のことだ。
大公「陛下」などはこの五年間靴下すら新調なさらないし、妃殿下も年に一着ドレスを作れば良い方だ。
さすがに育ち盛りのクレール姫は、年に二着ほど新しい服を作られるが、それにしても、材料は父陛下と母殿下のお下がりをリサイクルした物、でまかなわれている。
国一番の匠達は、そういった訳で「本来の仕事をしているだけ」では、そのすばらしい腕前を無駄に休ませ続けることになる。
俸禄は他の女官達同様に十分なものを与えられているから、年三着ドレスを仕立てるだけでも、楽な暮らしができる。が……。
彼女たちは酒精中毒(アルコーホリック)ならぬ仕事中毒(ワーカーホリック)で、とにかく何か仕事をしていないと落ち着かないという性分だった。
大臣達の朝服から、料理人のエプロンまで、宮中で使用するありとあらゆる布と糸との創造物を、新調しなければならない都合が生じたら、すぐに彼女たちが動き出す。
さすがに陛下が「メイドの仕事を奪ってはならない」と命ぜられて以降は、シーツの繕いに手を出すことはなくなった。
しかし、主家が贅沢嫌いであるから、家人も自然節約を好むようになっており、メイドの仕事が増えることはあっても、仕立屋の仕事は減る一方である。
そのためノルナ姉妹達は、それまで大公宮の中にあった自身らの作業所を、垣根の外側に移した。
そこで臣民の、特に女房連に、仕立や刺繍、レース編みなどを無料で教授しているのだ。
彼女たちの暇つぶし(こう表現すると、ノルナ姉妹は非常に怒る)は、名産の絹縞をより良質にすることに、役立っている。
クレール姫はノルナ姉妹の様子を、工房の窓からちらと覗くと、驚いてガイアの顔を顧みられた。
「私は並の体つきではありませぬ。ふつうの型紙をふつうに手直しするだけでは、デザイン帳通りのドレスは作れぬのです。そうなると、裁断も縫製も、ふつう通りには行きません。刺繍やレースの図案も当然工夫しないといけない」
ガイアは静かに言った。
「つまり、ふつうならば三ヶ月あれば充分仕立てられる衣装も、要らぬ手間が増し、四ヶ月以上かけねば完成させられないのです。……それを彼女らは、無理を押して三ヶ月で作り上げようとしています」
工房の中では、三姉妹が、文字通り髪を振り乱して働いていた。
それほど広くない部屋の中に、ボディとかマネキンとか言うらしい首のない大きな人形が幾体も並んでいる。
そのうち何体かは裸で、何体かには型紙を張り合わせたものが着せられ、何体かは仮縫いのまま作業を止められた物を着、何体かは「失敗作」を着ていた。
何日か前(ギネビア女王の使者が来る以前)、私とガイアが覗いたときと比べて、仮縫いを着た人形の数が一体少なく、失敗作を着た物が一体多い。ただ、錯乱した状況はその時と今とで大差がなかった。
「ああ、良く来てくださいました。ファデッド様、もう一度、胸回りの採寸をさせてくださいませ。それからクミン様、肩幅を確認させていただきます」
イフィゲニアが言い終わるのと同時に、オレステスがガイアに、エレクトラが私にメジャーを巻き付けた。
「衣装が完成したと聞いて、見に来ました」
私が言うと、
「誰が、そのような無責任なことをお耳に入れたのです?」
イフィゲニアは目を丸くして、それでもヴェールの一部になるのであろうレースを編んでいる手を休めずに、尋ね返した。
「少なくとも、私の目には、完成品が並んでいるように見えるが」
小さなため息の後、ガイアが言う。
私の目にもそう映っていた。
「ファデッド様の体型を美しく演出するラインが、どうしても作れないのです。なにぶん、ファデッド様のお体と言ったら……」
言いかけるエレクトラの口を、オレステスが押さえ込んだ。
「構わぬ。私は、己が女離れしていることを、ちゃんとわきまえている」
剣術の匠であるガイアは、確かに一般的な女性の理想とする体型とは、全く異なる体躯を有している。
背は高いし、肩幅は私より広く、腕も足も筋肉によって太い。腰は確かに細いが、それはコルセットで締め付けた不自然な曲線とは違い、無駄な肉の削げた自然な線を描いている。
「その演出という言葉に、矯正という意味が含まれているとしたら、私はあなた方の方針に、反意を申し上げるしかありません」
私の言葉に、イフィゲニアはようやく手を止めた。
「ビスチェで持ち上げたあふれそうな胸元や、コルセットで締め上げた細い腰、ペチコートで水増ししたふくよかな臀部は、私のガイアの魅力とは反するものです」
私は言った後、そっとガイアの顔を見た。本音ではあるが、失言でもあった。
彼女が女性として失格であると宣言したのと同じではないか。
ガイアは瞬間困惑顔をした。だが、
「パットで広げた肩や、入れ子でふくらませた腹回り、タックで広げた腿は、私のレオンの魅力とは反するものであるから」
と、笑った。
その時、私達はノルナ姉妹にふつうの礼服を作ってくれるように頼み(ガイアは「私もそれと同じもので構わない」などということまで言いもした)、工房を後にした。
しかし今、失敗作を着た人形が増えているところからすると、彼女たちはどうしても「美しいドレス」を作りたいようだ。
勢い「結婚式」は、本人達より周りの者達の方が張り切るもの……らしい。
ところが、期限は近づく。国一番の職人の名誉ゆえ、妥協する事はできない。
姉妹達は寝食を忘れて、作業に没頭していた。
「休むようにご命令いただけませんか? 熱心が過ぎて、私やクミン卿の声は届かないようなのです」
そう懇願するガイアの顔と、隈と疲労に覆われたノルナ姉妹の顔とを見比べ、姫は小さく頷かれた。
翌朝、早く。
私は一疋(二反)の白絹と三人の従者を携え、出立した。
東の国境まで並足で小一時間。傍らに、ガイアがいた。
街道は、落葉松の並木である。
木漏れ日が虹のように降り注いでいる。
私たちは、特に会話することなく、視線を交わすこともなく、ただまっすぐ馬首を並べ、ただまっすぐ道を進んだ。
やがて、申し訳程度に道を塞ぐ簡単な木の柵と、粗末な番小屋が見えた。
形式として、大公「陛下」の勅命書を読み上げると、番兵が最敬礼の後、木戸を開けた。
ゆっくりと木戸を抜け、振り返ると、柵の内側でガイアがようやっと口を開いた。
「安心しました」
彼女は私の顔をじっと見つめて言った。
「安心ですか?」
「あなたの背中が、力強いので」
とたん、私は背に何か負ったような気になった。ガイアが私に寄せる信頼は、大きく、また重かった。
厚い唇が弓のようにしなった。彼女の笑顔は、いつも力強い。
と。
柔らかい陽光を浴びるガイアの体に、赤いもやのようなものが被さるのが見えた。
もやは蛇のようにうねると、彼女の右腕にまとわり付いた。
私は瞬きをした。
わずかな暗転の後、目を開けたときには、もやは消えていた。
いや、最初からそんな物はなかったのだ。木漏れ日の光加減だったのだろう。
「では、行って参ります」
私が言うと、ガイアは無言のまま、左手を挙げて応じた。
赤い石のはまった指輪が、光をはじいて輝いた。
天空は、どうやら強い東風らしい。良く晴れた青い空を、いくつもの雲が流れている。

「振られてしまいましたよ」
と、実にあっさりした笑顔で、フレキ皇弟殿下は仰った。
当人達が全く乗り気でない政略結婚である。口にすることは決してできぬが、双方、何とかしてこれを破談にしたいと願っていたのだ。
「『わが夫は国家なり』だそうです。……良い言葉だ。誰の入れ知恵でしょうかね」
楽しげな視線が、私に注がれている。
「さて……」
私は……ガイアがひどく嫌っている……社交笑いを浮かべて
「私はただ、故事を暗唱しながら、女王に絹織物を献上しただけですから」
六百年以上昔。
まだジン帝国による統一がなされる以前、大陸には、村と呼んでもよいぐらいの小国が乱立していた。
その一つに、お家騒動が起こった。
王の嗣子に母親違いの妹を娶せるという、「血統を守るための結婚」が、遠因であった。
母のみが血が同じということと、父の血のみが同じということに、何の違いがあるのか知れないが、異母兄妹(姉弟)の婚姻は認められ、異父兄妹(姉弟)のそれは禁忌とされている。
現在でも、それは違法ではない。行う者がほとんどいないというだけである。
ただし、実の……つまり、父も母も同じ……兄妹(姉弟)の結婚は太古より禁じられている。倫理としても、遺伝学の見知からも、当然のことである。
さて。
その国の妹姫には恋人が居た。姫と兄王子との縁談さえなければ、彼は伯爵くらいには成れたかも知れなかった。
その男は婚儀の三日前の深夜に、嗣子を殺してしまった。
愛か、欲か。理由は定かでない。なぜならことを成し遂げた直後、彼は衛兵に膾(なます)にされてしまったのだから。
空位となった王太子位を、嗣子と同腹の弟と争ったのは、嗣子の妻となるはずだった異腹の妹であった。
無為な闘争を避けようと、同腹の弟は妹(彼にとってはほんの二日違いなのだが)に、自分との結婚を提案した。
そのとき彼女が言ったのが、先の台詞である。
結局、王位は妹が継ぎ、弟は摂政となった。女王は生涯結婚することなく、死後、御位は弟の子が継いだ。
「まあ、貴君はそのためにユミルに来たのだろうから」
この場合の「そのため」が、私の言葉のどこにかかるのかが、微妙で重要な点である。
フレキ殿下は、清々しい笑顔を作られた。
……すべてを知っている、予も感謝している……
そのような殿下の声が、聞こえてきそうな笑みであった。
ヨルムンガンド・フレキ=ギュネイ公爵一行がユミルに到着したのは、私に遅れることわずか3時間だった。
私はギネビア女王の「声なき依頼」を遂行することに、ぎりぎり間に合ったということになる。
ユミルは小さな島国であるから、国賓が泊まる宿も、小さく狭い。
世が世なら皇帝であられた皇弟フレキ殿下と、世が世なら僻地の小役人に過ぎない私とが、ラウンジで差し向かいにお茶を飲める光栄は、他の国では味わえまい。……いや、わがミッドでもあり得るか……。
そう。
私と同じ卓で私と同じ「一番安いお茶」を注文したフレキ殿下は、数年前まで先帝の第二皇子であられた方なのである。
上等だが時代遅れの衣装を美しく着こなし、長めの髪をうなじで結いまとめた、古風で上品な元皇子は、正に運に見放された人物であった。
第一皇子フェンリル=ギュネイとは同い年であり、且つ、皇帝たる資質は……政治手腕が、というよりは、カリスマ性が……兄以上と目されていたので、一時期は太子に立てられるのではないかとさそさやかれていた。
しかし、それは成らなかった。
皇帝の死が唐突に過ぎ、遺言が残されていなかったというのも、理由ではある。
父の妾姫ゲルトルートが産んだフェンリルが、たとえ半月ばかりの違いとはいえど紛れもなく第一皇子であったということも、また理由である。
だが。本当の、深いところにある理由は、外部の者には知れない。
おそらく、年長の順列であるとか、才能の優劣であるとか、そういった正論を越えたところで、天下は転がったのだろう。
ともかく二代皇帝の即位には、百姓(ひゃくせい)万民、何かしら策略めいたモノを感じていた。
フレキ殿下は、私と八つほどしか違わないはずだが、ずいぶん老成して見える。
顔立ちは彫り深く、目元に知的な輝きがあり、口元にお優し気な笑みがある。
その穏やかな容貌は、父皇帝よりも、生母であり先帝の正妃であったファンティーヌ妃のそれに強く影響されているという評判であった。
ともかく、帝位に就けなかった殿下は、幽閉に近い転封により、北の国「ガップ」の統治者となった。
我が祖国ミッドのおおよそ半分の国土に、やはり我が国の四分の一の領民が住む、芥子粒のような国である。
寒さが厳しい上に土地が痩せており、農産物の自給は望めないという。
海に面してはいるが、海岸線が険しく、港を作ることすらかなわない。
貧しい国である。
皇弟は、男女併せて十余名の従者と、二十名に満たない衛兵とに傅(かしず)かれ、自ら菜園を耕す日々を送っておられる。
その数少ない家臣の中には、兄皇帝の命を受けた監視役が混じっている。
やましいことなど何もなくとも、見張られるということは、心苦しい。
殿下はさぞ心穏やかからぬ日々を送られているのであろう。旅の空にある今、じつに晴れ晴れとした御顔をしておられる。
この旅に連れてきた供は、厳選されたたった2名である。
その、隆とした剣士と凛とした侍女は、忠実な家臣である以上に、信頼の置ける友であるようだ。
「義兄陛下は、ご息災ですか?」
穏やかで静かな声で、皇弟殿下は訊ねる。
大公妃・クリームヒルデ妃は、今上皇帝の異父姉である。
血縁が非常にややこしいのだが、今上帝と異母兄弟であるフレキ殿下とは、「他人」であった。
それでも、殿下は姉と慕っておられる。
そして、姉の夫である我が主君をも、兄事してやまない。
「我が君には心身とも健勝にございますれば」
返事は、なかった。小さく、満足そうにうなづかれただけである。
皇弟殿下が
「ミヒェル、ガービ」
と小声で呼ばわると、二人の従者がすっと両脇に付いた。二人が殿下に頭を垂れ、また私たちに礼をするのを合図とするかのごとく、殿下も立ち上がられた。
殿下は背が高いゆえ、がっしりとした骨太であるにもかかわらず、細身に見える。
「ご出立には、時間が遅うございませんか?」
日が暮れかかっている。
出口に向かう後ろ姿に問うと、殿下は振り向き、
「フェアカゥフ行きの最終便まで、あと半時……ゆえ」
笑顔は崩されなかったが、しかし寂しそうにこう言われた。
「義兄陛下に……おそらく、もう二度とご尊顔を拝することはできますまいから……愚弟が北の果てからご息災を祈っておると、お伝え願いたい」
後味が悪い。
婚姻によって儘ならぬ国をつなぎ止めようという策を、ギュネイ帝室は好んで使う。
我が主君の結婚もそうであるし、先年は豪商の孫で九歳になる男子に、二十歳を越えた異母妹を嫁がせもした。
それによって嫁ぎ先を手中に押さえ込めるのならば、それは……道義はどうあれ……政策として正しいだろう。
だが、かつては政敵でさえあった弟(ご本人にその意思はなかったと思われるが、少なくとも、今上陛下の家臣と皇弟殿下の旗本とは、かつて仲違いしていた)と、造反する力のある属国の女王とを一つに併せて、何の得があるのか?
顔を伏せた。飲みかけのお茶はカップの底で冷え切り、陰鬱な光を反射している。
私はつたない脳漿をフル回転させ、陰湿だが効果的な、そして当て推量にすぎない策略を思いついた。
本人達に叛意はないが、周りから見ると離反するように見えてしまう者達をわざわざ一所に集める。
そして、反乱軍の旗揚げのために財力と兵力を集めているという風聞を市井に流す。
判官贔屓が好きな市民は、大喜びで『零落した真の皇帝が、ついに圧政を引く偽帝を討つ』などと、尾ひれを付けた噂を広げる。
噂に信じ込む……フリをして、国家反逆の冤訴をでっち上げ、勅令を発する。
首謀者としてフレキ殿下とギネビア女王を含む、幾人か処刑……いや、フェンリル帝のことゆえ、一罰必戒であろう。
一国を完膚無きまでに叩き、三族殲滅させて、他国を戦慄させるがやはり得策か。
ともかく、一度の行動で、危険な政敵を滅ぼし、富を産む国を手中にできる。
声に出すつもりはなかった。
しかし無意識が、私の唇を動かしていた。
傍らにいた秘書官のロベールが、
「閣下」
と、一言発した。
ここは、交易盛んなユミルの、各国要人や商人の集まりうる場所である。
この、長い独り言は、不用意を極めていた。
この日ほど私は、自身が部下に恵まれていることを実感したことはない。
不相応な高位を与えられ若輩者に、主君は経験深い者達を補佐官として配してくださった。
ロベールも、四十を過ぎた中年である。二十歳も年下の私を、良く助けてくれる。
無駄口をたたくことがなく、適切な発言を多くする。
「うむ」
私は顔を上げ、笑顔を作った。
「明日、女王の晩餐会に、招待されていたましたが……」
普段と変わらない声音で、私はロベールに確認した。
ロベールは、頭からすっぽりと白い「雲」に包まれている。
私の表情は変わらない。私にとっては見慣れた光景なのだから。
彼は、白い濃霧の向こうで、私の考えを代弁してくれた。
「やはり、お辞めになりますね?」
「モーニングは用意してきたのですが、イブニングは忘れましたからね」
最初から、夜会服など用意していない。
そう。私は笑んでいた。
ありきたりの、ふつうの笑顔を浮かべていた。
対峙する者の頭上に「雲」が浮かんでいるのを見てしまったときの贋物の微笑を、いつも通りに作っていた。
たとえそれが、友であっても、親族であっても、私は心の奥の動揺と悲しみを顔に出さない。
幼い頃からの「訓練」によって、驚きを面に出すことができなくなっている。
だから誰も気づかない。
私が、その者の死期を悟ってしまったことを。

翌朝、私は出立を前に今一度ギネビア女王に謁見した。
「皇弟殿下といい、貴公といい、用が済んだ後に遊行しようという気がないのですね」
ギネビア女王が笑われるので、
「貧乏暇なし、でございますれば」
答えて一礼した。
「お国で良きひとが待っておられるのでしょう? 憎らしいこと」
女王の悪意のない嘲笑は、実に晴れやかだった。
私は、凍った笑みを浮かべていた。
衛兵の多くが、白い“雲”を負っていた。
ギネビア女王は、幸い……あるいは不幸……なことに、“雲”を頂いておられない。
いや、城中の者ばかりではない。登城の道すがら見かけた人々の大半が、“雲”の中にいた。
この国に、何か凶事が起こるのだろう。
だが、それを眼前の国家元首に伝えられるだろうか?
『多くの臣民が、近日中に命を落とします』
そう進言したとして、その理由を問われたとして……ガイアが認めてくれたように、ギネビア女王が理解してくださるはずがない。
いや、万一理解が得られたとして、何をどうすればよいのかは私にも判らないのだ。
私は何も言えなかった。
何も言えぬまま謁見室を出、何も語らぬまま城をあとにした。
必要なこと以外はしゃべらないという私の「特徴」ゆえ、従者達は私が黙することを不審がらなかった。
彼らは私にしか見えない“雲”の中で、故国に帰れることを素直に喜んでいる。
私は、喜べなかった。『この場の全員が死ぬ』ことが「見えて」しまっているのだ。
私が今抱いている冷たい感情は、聖職者がいう「悟り」などという崇高なものでは、おそらく無いであろう。
学者の言う「学習された無力感」というものに違いない。
私に、死を食い止める術がないことは、解っている。
泣いても騒いでも無駄なのだから。
港に着き、昼前に出航する定期便を待つ時間つぶしに入った付属の喫茶房で、私は飾ってあった鏡を見た。
映る虚像が、白く霞んでいる。
『私も、か』
驚くほど冷静に、私は直感した。同時に、
『ガイアの頭上に“雲”を見たなら、私はこれほど冷静でいられないだろう』
とも。
それはさておき。
大陸とユミル本島とを往復する船が、ようやく港に入った。
多くの降客と乗客で、港はごった返している。
「お疲れですか?」
ロベールが私の顔をのぞき込んだ。
「そう、見えるますか?」
「お顔の色が、お悪うございますよ」
「元から、そうでしょう?」
私は必死で笑った。
実は、少々吐き気がしていた。
芋洗いに込み合う人の群が、みな白や黒の“雲”を引きずって歩いている。
『ここにいる全員が死ぬ』
かつて見たことのない数の「死神」に、さすがに圧倒されてしまった。
『火山かと思っていたのだが。それにしては山手を離れた海岸線の者の方が、“雲”に憑かれている確率が高いのは、妙だ』
腕組みし、見返る。
ユミル本島の中央部にそびえる活火山が、一筋の噴煙を上げていた。
『やはり違う』
直感めいたものが、私の脳裏に浮かんだ。
『自然災害ではない。もっと禍々しい「死」が近付いている』
顔を、港の側に戻した。
海は見えなかった。変わりに人の顔があった。
「ミッド公国の使節の方とお見受けするが」
その顔は、生臭い息を私の鼻に吐きかけた。
この人物は、それほど近い位置に立っていたのだ。
私はこの人物を知らない。
しかし、彼の隣に、意外ではあるが、見覚えのある顔があった。
何故意外か。
その人物レイモンド・ノギアは、ユミル女王国の対岸、大陸側にある直轄地クォイティエの豪商で、代官を任ぜられている。
代官が任されている領地から出ることは、ほとんどない。
何故見覚えがあるか。
それはクォイティエを通らねば大陸東南部へ旅することができず、クォイティエを抜けるためには代官の許可が必要とされているからだ。
口臭のする男は背が高く、一見兵士風の姿をしていた。
ひげも眉も髪も、湯煎に失敗して焦げたチョコレートのような色をしている。
レイモンド・ノギアは、矮躯だった。
丸々としたワイン樽のように太っていて、役人にはとうてい見えない派手な衣装をまとっていた。
ノギアとその連れも、“雲”を負っていた。
赤黒い“雲”である。
静脈を流れていた血液が、何かの拍子に体の外へ出て、酸化を始めたような、どす黒い赤である。
初めて見る色合いであるが、紛れもなく“雲”であり、死の象徴だった。
「勅命なり」
ノギアはボールのような顔で私を見上げた。
「ギュネイ皇帝の、ですか?」
「【皇帝】のです」
太った兼業代官は、復唱するように答えると、にたりと笑った。
「拝聴しましょう」
そう答えざるを得ない。陪臣ではあるが、私もいわばギュネイ皇帝の家臣である。
「ミッドの国に、死を賜る」
言った直後であった。
ノギアの体が大きくふくらんだ。
比喩ではない。本当に巨大に膨張したのだ。
ふくらんだ体のあちこちが裂け、そこからどす黒い液体が噴き出した。
「閣下!」
私の体を、ロベールが突いた。
軽い体は吹き飛ばされ、私のいた場所に代わって立つこととなったロベールに、その黒い液体が降りかかった。
液からは、三百年かけて腐らせた葡萄酒のような、すえた臭いがした。
ロベールは
「ギャ」
悲鳴を上げると、床に倒れ込み、のたうち回った。
皮膚が、そして肉や内臓が、煙を上げて溶けてゆく。
苦しみは、短かった。
信頼すべき優秀な男は、あっという間に骨になっていた。
悲鳴は、その場にいたミッド使節とは無関係の人々の口からも発せられた。
飛び散った液体を浴びた者は皆足掻きながら溶解し、人の形を失った。
一難から逃れた人々が、出口に殺到した。
その群に、もう一人の男が錆びた巨大な鎌を振り下ろした。
先ほどまであの男は、そのような物を持ってはいなかったはずだ。
目を凝らして見る。すると、その鎌の刃が、彼の両腕から直接生えているのが見て取れた。
何が起きたのか、理解できなかった。
理解できぬまま、私は床を転がった。
ノギアは膨張した体から、強酸と思われる液体を吹き出し続けているし、兵士風の男も、無闇に鎌の付いた腕を振り回している。
「よりにもよって、こんな死に方か」
本音というものは、弱気なときほど口をついて出るものだ。
理解のできない現象、理解のできない物体によって、理解のできない最期を迎えるのは、理不尽というものだ。
たしかに、死という結果は、例えどこでどのように迎えようとも同じであろうが、やはりそこへ向かうプロセスが重要ではないか。
ふ、とガイアの顔が浮かんだ。
『あなたの背中が、力強いので』
出立の時の彼女の声が聞こえた気がした。
この瞬間、私は
『死ぬなら、ガイアに看取られたい』
と、痛切に思った。
直後。
私はすぐさま理解しがたい現実に引き戻された。
《往生際の悪い小僧め》
腐ったワイン樽が口をきいた。
数分前までノギアだった物体は、最初よりも大きくなっている。
足下から管状の物が伸び、それが強酸を浴びて溶けた遺骸に絡まっていた。
この物体は、生き物に酸を浴びせてタンパク質を溶解させ、養分として吸収しているのだ。
混雑していた港にいた人々の、おおよそ半分が、その物体にのタンパク質を吸収されたようだ。
それによって、レイモンド・ノギアだった物の身体は、自重により歩行することが困難になるほど肥大していた。
私に対して酸を吹きかけようとしているのだが、そのためにその場から動こうとすることはしない。
私はウツボカズラやハエトリソウの類を思い浮かべた。
《オルロイ、あの餓鬼を引きずり出せ! 【皇帝】の命は、ミッドの殲滅だ》
私が物陰……待合所の柱だったか、あるいは破損した壁であったか、思い出せない……に隠れているが故、自身の酸や養分を吸う管が届かないことに、ノギアはいらだっているようだった。
私もいらだっていた。
死は、どうやら避けられそうにない。自身の「能力」によって、それを悟ってもいる。
しかし、その原因が正体不明なものだということが、気に入らなかった。
大体、ノギアの言う「【皇帝】」とは何者か? ギュネイのそれか、あるいはあの化け物達が、自身を統べるモノをそう呼んでいるだけなのか?
どちらであるにせよ、何故その「【皇帝】」がわがミッドを滅ぼさんとしているのか?
そして。
本国は今どうなっているのか?
ミッドにもこの様な輩が現れ、この様な殺戮を行っているのか?
判らないことだらけだ。何もかも。
私は理由や原因を考えようとした。
思えば悪い癖だ。理解できないことを理解しようと努めること自体は、紛れもなく良いことなのだが、私は所構わず思考を開始してしまう。
その時も私の癖は、それを気付かせなかった。
ノギアが「オルロイ」と呼んだその蟷螂のようなモノが、私の真向かいに立っていること。そしてソレの鎌が私の右肩口へ振り下ろされたことも。
痛みが、全身を貫いた。
光が一瞬で失せ、私は闇のただ中に放り込まれた。
やがて、景色が脳裏に浮かんだ。
絶望的なその光景は、しかし現実の物ではなかった。
どこかの医療施設。
設備はお世辞にも整っていると言い難い。
にもかかわらず、患者が次々と運ばれて来る。
死病が蔓延しているのだ。
看護婦のみならず、立って歩ける者総てが「私」の指示通りに動いてくれている。
だが、患者は皆死んでゆく。
治療薬の絶対数が不足している。その少ない薬を投与しても気休め程度にしか効かぬ。
どんなに尽力しても、及ばない。
「私」も罹患している。目が霞み、意識はもうろうとしていた。
やがて、一人の看護婦が倒れた。
誰よりも良く働いていた者だ。
誰よりも大切な女性だ。
「私」は叫んだ。
『死なせない! 私はお前を死なせたくない!』
目の前が赤く染まった。
「ガイア!」
現実の私が叫んだ。
切り裂かれたらしい肩口に、痛みはない。
オルロイは毛の生えたトカゲのような顔を、驚愕で満たしていた。
やがてソレは私から目をそらし、
《吸えない!》
と叫んだ。視線の先にはノギアがいるようだ。
《なんだと!?》
ノギアの声が応える。
ソレが「吸う」のは、おそらく人の命だと思われる。
奴らは人の命を大量に消費して「生きて」いるらしい。そうせねば「生きて」いられないのだろう。
オルロイの驚愕は、悲鳴に変わった。
《吸われる!》
私は、刃の先から強烈な「悲しみ」が体の中に流れ込んでくるのを感じていた。
オルロイの腕はいつの間にか鎌の形状を失っていた。
人間のそれに戻っている。それも、朽ち木の枝のように細い腕だ。
私はその痩せた腕を掴んだ。
自慢できるほど腕力のない私の微々たる握力に、そやつの腕は粉々に潰れ、折れた。
まるで、賞味期限の切れたクロワッサンを握りつぶしたような感触だった。
私は己の右肩口を見た。
斬られた痕はない。衣服も裂けていない。
だが確かな変化があった。
肩が光っている。赤い光を発している。
その光が叫んでいる。
『死なせたくない! 死なせたくない!』
「私も……私も死なせたくない」
一瞬の闇に見た幻。その中で命を落とした女性の苦しげな顔と、故国で待っているはずのガイアの顔とが重なって見えた。
《盗られた! アームを盗られた!》
わめきながら、オルロイは両膝を落とした。
途端、彼の体は軽い破壊音を発しつつ、バラバラに砕けた。
「アーム?」
オルロイの最期の言葉を、私はかつて聞いたことがあった。
この世に未練を残して死した者の骸が、一個の赤い石に転じたという昔話。
そして、思い出した。
その赤い石が、不思議な力を秘めた武器になるというおとぎ話を。
私は私の中で叫んでいる無念の魂に呼びかけた。
「古の仁者よ、私と共に人を救い給え」
肩の光が、いっそう強くなった。血液が沸騰したのではないかと思うほど体は熱く燃え、力がみなぎるのを感じる。
そして「彼」の名が、私の脳裏に浮かんだ。
「【死】!!」
光が長い竿状に伸びた。私が掴むと、その先がほぼ直角に折れた。
麦を刈る巨大な鎌、絵本に描かれる死神の鎌そのものの形状だ。ただし、鮮血のように赤い。
私は物陰から出た。
腐ったワイン樽が、たるんだ皮膚を震わせている。敵の出現などはまるで想定していなかったのだろう。
《オーガからアームを奪って……ハンターになっただと?》
「オーガ……。そうか、それが貴君らの総称なのですね」
不可解が一つ消えた。
「とすると、ハンターというのは、貴君らを倒す者のことですか」
私は、私自身が驚くほど冷静になっていた。
逆にノギアは激しく狼狽していた。
「貴君が言う【皇帝】は、貴君らの統治者のことなのですね?」
答えはない。
「何故、貴君らの【皇帝】は、ミッドを殲滅せよ、と?」
土気色の首が、横に振られた。
《知らん。ただ命令されただけだ。ワシは知らん》
「その命を受けたのは、貴君らだけではない……輩が、本国に赴いている?」
今度は首を縦に振る。
「そして貴君と同じように、手当たり次第に人の命を奪っているのですね?」
《ニンゲンとて、牛や豚を屠殺して喰うではないか》
ノギアは相変わらず震えているが、どうやら嘲笑する元気だけは取り戻したようだ。
「だが、野生の猪は牙を持ち、野牛は角を持っています。彼らは生きるために戦い、生きるために抵抗する」
私は赤い鎌の柄を強く握りしめた。ゆっくりと、ノギアに近付く。
ノギアは明らかに動揺していた。
虚勢ともとれる大声で、
《人間は死ぬ。だがワシらは死なぬ。人間を喰って、生き続ける》
吼えると、体を大きくふくらませた。
全身から強酸が吐き出た。
周囲には、まだ数名生き残っている者がいたが、標的は私一人に絞られている。
私は手にした鎌を前に突き出した。
考えて取った行動ではない。
歩くときには両足が自然に出るが、それは一々「右足を出して大地を踏んだら、左足を蹴って前に出し、それが大地を踏んだら、今度は右足を出して」などと考えながらやるものではないだろう。
それと同じだった。避けようと思ったら、そうすることが当然のように、体が動いた。
強酸は鎌に触れるや否や、白煙を上げて蒸発した。
私には、ほんの一滴も降りかからなかった。
ノギアは驚き、また恐怖したようだ。
「死は総ての生き物に訪れる。逃れることはけしてできない。当然、私もやがて死ぬでしょう」
私が言うと、ノギアはでっぷりとした体を揺すって、必死に後ずさろうとした。
ところが、肥大した体は一寸も動かない。
「私はつい小半時前まで、死を待っていました。仕方のないことだと、あきらめていました。……ですが、今後は直前まで戦って、間際まで抵抗することにします」
私は鎌を振り上げた。
「死は万民に平等。況や、オーガをや」
振り下ろした鎌の刃に、私は、チーズを切ったほどの抵抗力も感じなかった。
港で何か変事が起きたという知らせを受けて、武装した師団が到着した時には、全てが終わっていた。
かろうじて難を逃れた人々が、衛生兵に促されて医者の元へ進む。
相変わらず“雲”を負っている者もいるが、大半の頭上からそれは消えていた。
そして、今朝方私が城中で出会った“雲”を頂いた兵士も何人か出張って来ていたが、彼らの内で今もって“雲”に取り憑かれている者は一人としていなかった。
私は師団長に見たことありのまま話した。
惨状はその場にあるのだが、師団長は
「それでも信じられないし、復命のしようがない」
と、私自身がギネビア女王に報告して欲しいと言った。
私は断った。
母国のことが、主君のことが、そして何よりガイアのことが案じられた。
「足の速い船を一艘、お貸し願いたい」
無理矢理頼み込み、小さな漁船を借り受けた。
故国を出るとき3名だった従者は、馬丁ただ1人になっていた。
しかし彼も重傷を負っていたので、ユミルに残すことにした。
私はただ一人、老練な漁師とその子弟が操る船に乗り込んだ。
ほんのわずかな手荷物と、一つの珠を手中に握って。
レイモンド・ノギアを人外の物に変貌させた原因の一つであるそれが、「【節制】」という銘のアームであるということを私が知ったのは、随分と後になってからのことだった。

私は、ある意味で遅すぎ、別の意味では間に合った。
たどり着く直前に、故国ミッドは壊滅していた。火山の噴火により……と、救助活動を行った隣邑の役人は言った。
実際、硫黄の臭いと噴煙の霞とが大地を覆っている。
同時に灰色の「雲」と胸が悪くなる「気配」も、空に充満していた。
国民は亡骸で見つかるか亡骸さえ見つからないかのどちらかで、生き延びた者を数えるには十指で事足りた。
その指の中に、彼女はいた。
医者は複雑な顔で言う。
「生きておられます」
医者の言葉を訊いた瞬間、私は喜んだ。大公一家が行方不明であることを一瞬だが失念し、驚喜した。
だが。
「前のめりに瓦礫の中に倒れ込んだのが……幸いと申しましょうか、あるいは不幸と申しましょうか。噴火の熱波が背中の上を通過した様子で……」
医者ははっきりしない口調で彼女の様態を説明しようとしていた。
当たり障りのない言葉を選ぼうとする彼の発言など、私のは不要だった。
粗末なベッドの硬そうなマットにうつ伏せで寝かされている彼女の姿を見れば、彼女がどのような傷を負っているのか見当が付く。
小さな個室にぽつんと置かれたベッドの中で、ガイア・ファテッドは昏々と眠っていた。
そして大柄な彼女の総身は、真っ赤な「雲」に包まれていた。
前のめりに倒れていたという彼女の身体は、確かに裏側……ふくらはぎからつむじまで……の皮膚だけを、ムスペル火山が吐き出した熱波に融かされていた。
長く艶やかだった黒髪はすっかり燃え尽き、わずかに前髪だけが、申し訳なさそうに額を隠している。
顔に怪我はなかった。しかし頬はやつれ果て、落ちくぼんだ眼球を覆う瞼は黒く鬱血していていた。
そして右の肩に、きつく巻かれた巨大な葉巻煙草のような腕がすげられていた。
「腕は……恐らく火山弾か何かが当たったか、瓦礫に挟まれたかしたのでしょう。剣を握ったまま押し潰されていました。何とか切断はせずに済みましたが、元通り動くようになるかは……」
「剣を握っていたのですか?」
聞き返すと、医者は小刻みに数回うなずいた。
彼女は常に帯刀している。普段は正装の一部として腰にサーベルを。武装する……闘技会であるとか、閲兵式であるとか、あるいは警備が必要な時……場合はもう一振り、背丈ほどもある幅広の両刃剣を背に負う。
「剣とは、サーベルですか?」
「いや、丸太のような長剣です。実を言いますと、それで身元が判ったのでして。つまり、ファデッド卿の剛腕は、近郷に広く知れておりまして……」
噴火のその日、何らかの理由でガイアは武装していた。そして、何事もなければ背に負っているはずの長剣を、押し潰された右腕が掴んでいた。
「抜き身でしたか?」
一応の確認をしてみた。医者の答えは予測できた。
「ええ……そうです」
「剣は、どこにありますか? ……あれは彼女の、剣士の『魂』ですから、傍らに置いてやりたいのです」
「そう言うことでしたらすぐにお持ちしますよ」
医者は疲れた笑顔を浮かべると、部屋を出た。
私は、ベッドの端にそっと腰掛けた。かすかな揺れが、彼女の瞼をわずかに開かせた。
「おはよう」
私は、自身が平静で自然な声を出したことに少々驚いた。
目覚め、私の顔を確認した彼女の第一声は、
「私は私でなくなってしまった」
である。
瞬間、返答にあぐねた。息を一つ呑む内に何とか絞り出した答えは、
「私には私のガイア以外の何者でもなく見受けられますが」
で、あった。
嘘を吐いたつもりは毛頭ない。彼女は紛れもなく彼女であった。
怪我を負っていても、やつれ果てていても、不吉な雲に覆われていても、目の前に横たわるのは、私の大切なガイアそのものなのだから。
だがガイアは、核心を突いた。
「そう『見える』だけでしょう」
苦しい息を吐き終わると、静かに瞼を閉じた。青白い頬を涙が一筋流れ落ちた。
ガイアが喘ぎながらも私に語ってくれた「ミッドに起きた悲劇」を要約すると、この様になる。
宴席に現れた監国謁者(目付役)のルカ・アスクが、突如得体の知れない物体に変じたこと。
彼……あるいは《それ》と呼んだ方が適切かも知れない……は両の手で「鎖につながれた獅子」に見えるモノを操り、破壊と殺戮を行ったこと。
その「獅子」に噛み付かれた者は精を吸い尽くされて死に、亡骸は出汁を取った後の鶏ガラさながらにやせ細っているということ。
命を失い、倒れ、動かなくなったそれらの亡骸が、しばらくすると起きあがり、《それ》の望むこと……殺戮と破壊……を行うこと。
クレール姫と控え室にあるとき混乱が起こり、従って大公殿下ならびに妃殿下とははぐれてしまったこと。
姫をかばいながらルカ・アスクだったモノに攻撃を加えたが、返り討ちに遭ったこと。
繰り出された「獅子」が
「私を襲い、右腕を喰い千切った」
こと。
痛みと出血のため、不覚にも気を失ってしまったこと。
しばらく後に起きた激しい地震に揺り起こされ意識を取り戻したが、直後吹き付けた熱波によって、再び気を失ってしまったこと。
気が付くとこの病院に居た。そして「国土は火山によって壊滅した」「国民の大半が死亡した」「大公一家の亡骸は見付かっていない」と聞かされた……。
「人でなくなったというのは、ルカ・アスクに喰い付かれて、人喰鬼にされた、という意味ですか?」
「それは違う。ヤツの奴隷になるのは、押さえられた」
枕に埋めた口から、くぐもった、しかし奇妙に楽しげな声が出された。
沈んでいて、且つ明るいガイアの言葉は、先に彼女自身が語ってくれた、「《それ》の犠牲になった者は、すべからく《それ》に隷属する魔物になる」という事実に反しているではないか。
「どうしてですか?」
言いながら「言葉に不信感が現れている」と感じた。そして当然ガイアもそれを感じ取っていると、この時は思ったのだが、後で彼女に……恐る恐る……聞いてみたところ、
「あの場合あのように反応するのは至極当然のことであるから、気にならなかった」
という答えが、笑顔と共に返ってきた。
兎も角。
彼女は顔を伏せたまま、右腕に巻き付けられた麻布をほどいた。
「貴男にも、火傷に見えますか?」
腕は痩せ細っていた。骨に皮が張り付いたような指先から二の腕までが、赤く爛れている。見覚えのあるこの「醜さ」が、私の目に火傷と映ることはなかった。(大体、これを「火傷」と断じた医者は、言っては悪いが藪以下であろう)
そう。
私はつい最近、遠く離れた島国の港で、その爛れ同様に「醜い」皮膚を持ったモノと出会い、闘った。
私が答えずにいると、ガイアはそっと顔を上げた。泣き腫らしたらしい赤い瞳が、私の顔を見て驚愕していた。
私は、恐らく笑っていたのだと思う。落ち着き払っていたことは憶えているのだが、表情までは記憶していない。
「《それ》は、貴女に何と言っていますか?」
そのび爛した腕に私が手を置きながら訊ねると、彼女の瞳の驚愕の色はますます濃くなった。
「《それ》が、私に語りかけているのが……判ると!?」
爆ぜるように身を起こし、そのため襲った激しい痛みに顔を歪めながら、しかし彼女は不安と驚喜の入り交じった眼差しを私に向けた。
「《それ》が私の知っているあるものと同一であるなら、対処の方法も……」
「……対処」
つぶやくように反復すると、ガイアの顔から驚喜が消えた。代わりに浮かんだのが、不安と安堵の交錯した微笑みである。
「貴男が来る直前、《それ》が面白いことを言ったのですよ」
「何と、です?」
「『殺される』」
「ほう」
「驚かないのですね」
「予想通りですから」
私が笑うと、ガイアは不安混じりの笑みを大きくして応える。
「《それ》は、貴男のことを【死】と罵っている」
「自分は何であると言っていますか?」
「【力】……誰よりも強い力だ、と」
「誰よりも、ね」
「『身体をくれれば、復讐のための力を提供する』とも」
「で、貴女は何と言って断っているですか?」
「復讐という言葉は嫌いだ、と」
「貴女らしい理屈だ」
「それに、どうやら《それ》自体が私の身体を用いて復讐を成したいだけのようなので。……私は他人に利用されるのも嫌いであるから」
「何故、《それ》の思惑が判るのですか?」
私はガイアの右手を撫でさすった。すると、皮膚の下で何かが痙攣した。《それ》はよほど私のことが気に入らないらしい。
ガイアは一呼吸吐いた後、思案しながら
「幻覚を見せられた。自分がいかに酷い目にあったのかを見せつけ、その瞬間を私に体感させてくれましたよ」
と、すがりつくような視線で私を見つめた。
どのような幻覚なのか具体的なことを言ってくれないのは、その光景がよほど凄惨で、思い起こしたくもないものだからであろう。
私はあえて幻覚の内容を聞かず、訊ねた。
「同情を強要するわけですね?」
彼女がうなずいて同意すると、彼女の右腕は激しく震える。そして、音でない声が、耳ではなく頭の中で聞こえた。
『強要? アタクシはただ理解して欲しいだけよ』
ガイアの右手の甲に血管が浮き出、大きく脈打った。ただ血液が流れているだけとは、とても思えない。
彼女は眉を顰め唇を噛んだ。右腕が激しく出鱈目に動いている。左腕で爪が食い込むほどに強く押さえ込んでいるというのに、赤い表皮に覆われた《それ》は、暴れることを止めようとしない。
やがて左腕をはね除けた右腕は、真っ直ぐに私に向かって伸びてきた。……比喩表現ではない。本当に、右腕が伸びたのだ。
掌が大きく開かれた。指関節が総てあらぬ方向に曲がっている。《それ》は関節という肉体の機能を完全に無視しているのだ。骨も腱も筋肉も、皮膚という袋の中に詰め込まれた挽肉の役割しか果たしていない。
太いが肉の足りない腐った腸詰めは、私の首筋に的確にからまりつくと、さらに伸びて、私の身体を向かいの壁に叩き付けた。
頭の後ろで、漆喰の割れる軽い音がした。
足の裏は地面の感覚を捕らえられない。
「確かに【力】と名乗るだけのことはあるようですね」
私はなんとか首まわりに空間を確保し、ようやくかすれた声を出した。
『アタクシの道を阻むことは許しません』
生暖かい肉の紐が言う。
「まるで威厳ある者のように語るのですね……死霊の分際で」
私は笑っていた。【力】を自称する《それ》が自信に満ちていることが、可笑しくてたまらなかった。
この私の態度が、《それ》の逆鱗に触れたらしい。
『死……霊……? アタクシが、死霊!?』
《それ》は小刻みに震えると、
『無礼を言うことは許しません!』
私の首を締め上げた。
気道が狭まった。喘ぎながら、私はガイアを見つめた。
彼女は、恐怖していた。
己の腕……だったもの……が、私を傷付け、苦しめている事実に、恐れ戦いていた。
「事実……ですよ。いや、死肉と言った方が……よいかも……知れませんが」
私は(恐らく、呼吸困難により青黒く変色した顔で)精一杯の笑顔を作った。
「死肉」
ガイアの小さなつぶやきが、私の鼓膜を力強く震わせた。それと同時に《それ》の大きな怒声が、私の脳髄を激しく揺すった。
『死肉!?』
肉の縄はいっそう強く私の首を締め上げた。
《それ》には、私の《それ》に対する見解を訂正させる気がないようだ。
そのような面倒な真似は好まない。否定する者、考えに会わない事象は、総て切り捨てる……それが流儀らしい。
「……生きて……いない肉体……は……死肉……で……しょう……」
息が詰まった。語尾を発声できた確信はない。しかし、言わんとした事がガイアに伝わったという確信はあった。
「剣をっ!」
部屋を震わす大きな声が、ガイアの胸から飛び出した。
私の右手側、薄汚れた壁を穿つ傾いだ扉が、声音に押され、錐で刺さるような軋み音をたてながら、勢いよく開いた。
その外側、狭い廊下で、重たい金属が床を打ちすえる音と、2人ばかりの驚声が聞こえた。縦長く切り取られた空間で、おどおどした二組の視線が泳いでいる。
一つは、私をここに案内し、ガイアの病状を解説した医者。もう一つは下男らしき小柄な老人のものだ。
二つとも、焦点が合っていない。
痩せ細った重体の怪我人が、右腕一つで大の男……私の体躯をそう形容してよいかどうかは兎も角……を吊し上げている。それもかなり不自然な体勢で。
医者は目を見開き、下男はしきりに瞬きをしている。現実を目撃しているという感覚は、この二人にはないのだろう。
「剣をっ、早く!!」
再びガイアが叫んだ。
その覇気で、下男が現実に引き戻された。
床に張り付くように落ちている重い金属の固まりを、医者と二人かがりで漸く運んできた長大な剣を、腰の曲がった彼がたった一人で拾い上げた。俗に「火事場の馬鹿力」というものであろう。続く、
「投げよ!」
というガイアの声が、さらに老僕を突き動かした。
彼は剣を放り投げた。長大な剣が、弧を描いて宙を舞った。
抜き身が、ガイアの足下に落ちた。
柄を、左手で掴む。掴み挙げる。逆手で突き上げる。切っ先が跳ね上がる。刃が左腕に当たる。
『何をするの!?』
《それ》が金切り声で叫んだ。
ガイアは答えなかった。
無言で、剣を振り抜いた。
腐った腸詰めの皮が破けた。
液体が吹き出た。血液ではない。アンモニア臭をまき散らす、腐った肉汁だった。
ガイアの身体から切り離された《それ》は、最初のうちは元に戻ろうと足掻いていた。ガイアの右肩につながって居たいと切望し……《それ》に意識というモノがあるのなら、だが……のたうちながら彼女ににじり寄った。
だがガイアが《それ》を受け入れるはずがない。
膝をつき、大きく肩を揺すってようよう息をしているのだが、彼女の眼光は覇気にあふれ、鋭かった。
赤紫色の乾いた唇から、地を這う低さの引導が溢れ出る。
「そこを、動くな……。切り刻んでくれよう」
彼女が杖とすがっている長大な鉄のかたまりが、人脂にまみれてぎょろりと光っている。
『ギィッ』
退路を断たれた《それ》は、新たな道を私の身体に求めた。
《それ》は最後の力を振り絞っていた。私の首にしがみつき、肉を食い込ませ、私の肉体に侵入しようとする。
『生きたい、生きたい、生きたい、生きたい』
腐肉は呼吸のように言い続けた。
私の首に巻き付く力は次第に失せてゆくが、それでも決して放そうとはしない。
私も必死だった。
爪を肉に食い込ませ、非力な力で《それ》を引き剥がそうとした。
必死と必死の争いは、どうやら私の勝利で決着した。
首のまわりの肉紐を何とか解し、ようやく呼吸の自由を得た私は、かすれた声で唱えた。
「古の仁者よ、私と共に人を救い給え」
肩に、熱を感じた。
『ギャッ!』
《それ》は悲鳴を上げて飛び退いた。床にぼたりと落ち、2度3度大きく痙攣した。
私は肩の「熱」を長柄物と変化させようとした。そう、あの時のように。
だが、止めた。
《それ》は、すでに自発的な動作を失っていた。床の上で、フライパンの上の牛脂のように形を崩してゆく。
溶けて、縮んで、干涸らびて、やがて枯れ枝ほどの太さと軽さの、死んだ右腕になった。
強烈な腐臭をあげるその物体からは、数え切れないほど大量の、肥えた蛆虫が川と這い出てきた。
その対岸で、ガイアが力無く倒れ込だ。
黄土色の汚物の川を、私は一足で飛び越えた。
抱え上げたガイアの身体は軽く、籾殻袋のようだった。屈強な剣士であった彼女が!
彼女を強く抱きしめたい心を、私は必死で押さえた。彼女が、手の中で崩れてしまうような気がしたのだ。
私はふと気付き、ベッドの上からシーツを引き剥がした。ごわごわした布を裂きながら、
「意識は、ありますか?」
恐る恐る、声をかけた。
ガイアは何も言えなかった。言えなかったが、幽かにほほえみを浮かべて応えてくれた。
私はこわばった笑みを返すと、ドアの方を見た。
そこでは医師と下男が、だらしなく腰を抜かしていた。
「腕を、切り落としました。腐って、思うままに動かせなくなっていた腕を、切り落としました。傷口の、処置を」
私が、裂いたシーツでガイアの右肩を押さえながら言うと、医師はがたがた震えつつもうなずき、四つん這いになってこちらへ近寄った。
その道すがら、彼は拳二つ分ほど身体をよじった。引きつった横目の先に、落ちた「腕」があった。
医者は三年物のチーズのように顔をこわばらせていた。
切り落とされたガイアの右腕は、その後、複数の医者によって検査された。
医師達は、
「神経も血管も筋肉も腱もズダズタに千切れている以外は、何の変哲もない腐乱死体である」
と断じた。
私もそれに同意した。事実それはただの肉塊であろう。
現場にいたあの医師と下男は当初納得しなかったが、医師団長が、
「皮下から微量の火山性ガスと腐敗ガスの混合物が見付かった。これは神経に影響を及ぼす可能性がある」
と言ったことにより、
『あの光景は幻覚』
と言うことで納得したようだ。
ガイアの回復力は驚異的であった。腐敗していた右腕を切断したのが彼女の身体にかけられて負担を軽減させたためであろう、と医者達は言った。
間違ってはいまい。事実に違いない。
ガイアの「右腕があった場所」は、皮膚を無理矢理に近い形で背中や胸から引っ張り寄せて縫合した、大きく攣った手術痕の中に埋没していた。
やがて抜糸の時を迎えた手術痕は、見ようによっては獅子の横顔の紋章にも思える赤い痣となっていた。
「快調ですよ」
相変わらず青白い顔をしたガイアは、しかし落ち着き払った声音で言う。
それなのに……ふわりとした彼女の笑顔が間近にあるというのに、私はまだ安堵を得ることができなかった。
私は「アームに心奪われた者は【オーガ】に堕ち、【オーガ】に堕ちたた者は死を迎えると肉体を失う」ものだ、と、命を総て使い果たして後、赤い宝珠「【節制】のアーム」を残して消滅したレイモンド・ノギアの様を見て、知っていた。
ところが。
ガイアが【オーガ】へ堕落しなかったのは、事件と負傷により心労はなはだしかったとはいえ、彼女の意志の強さが【力】に勝っていたためだと判る。
それでも右腕だけが魔物に転じたのは、それこそ彼女が心労はなはだしかったためであろうとも考え及ぶ。
しかし。
彼女を取り込むことができなかった【力】により【オーガ】とされたガイアの右腕は、切断され死を迎えたというのに、その形状を残したまま「【力】のアーム」に変化することがなかった。
何故だろう。
まさか【力】は未だにガイアに取り憑いているのではあるまいか?
私は凍り付くような焦燥に駆られ、思わずガイアを掻き抱いた。
背中越しに伸びた右腕の骨張った指が、ふさがれたばかりの傷跡に触れ多時、ガイアと私は同時に小さく悲鳴を上げた。
ガイアの悲鳴は痛みのためであろう。
私の悲鳴は、熱さのためであった。
およそ人間が……命持つものが発することはないであろう高熱。それは、私自身の身体がかつて発したことのある灼熱と、同じ感触を持っていた。
ガイアは脂汗の浮かんだ頬を震わせて、
「まだ【彼女】の声が聞こえます」
と、笑んだ。
悪い予感は当たっていたのか? 私は不安に駆られるまま、訊ねた。
「まだ復讐の勧誘をするのですか?」
「いえ……ただひたすら『生きたい』と繰り返すのです……ここで」
痩せ細った左の指先が、私の右掌の下を示した。
「【彼女】の叫びは私の胸を苦しめる。……私もそう思っております故。
命を持つものであれば、例え屠殺される定めの家畜であっても、儚い薄羽蜻蛉であっても、野の草木であっても、誰でもそう思っている。
だから私は……【彼女】を黙らせることができない」
風に吹かれた枯れ尾花のように、ガイアは私の胸に顔を埋めた。薄いシャツ越しに、涙が冷たく流れ落ちるのを感じる。
私は何も言えず、ただ彼女の背を撫でさすった。
肉のそげ落ちた肩が二,三度小さく揺れ、その後、一度大きく上下した。
「【彼女】を黙らせることができないと悟ったら、逆に胸のつかえが落ちたのですよ。私が生きている限り、ずっと【彼女】の叫びを聞き続けてみようとまで思えてきた。……可笑しいでしょう?」
ガイアは顔を上げた。頬の肉が痙攣している。唇は泣いているようだったが、目は笑っていた。
私の不安は、こうして消えた。
ガイアは、やはり強い女性であった。誰よりも強い人間であった。
私は私の人物鑑定眼に感謝した。
「それと……」
唐突にガイアは枕の下へ手を入れた。
ウエハースのように平らな枕と敷布の間から出てきたのは、ひしゃげた金の輪であった。
飾り気のないその小さな金輪に、私は見覚えがあった。
この古ぼけた、飾り気のない金の輪には、確か赤珊瑚の玉が付いていたはずだ。
「あの『事件』の朝、赤い珠が取れてしまった……。何とか嵌め込もうとしている内に気付いたのですが」
ガイアは「珊瑚玉」が付いていた跡の、曲がった縦爪の辺りを私に示した。
「何か、刻まれているのが見えますか?」
確かに「珊瑚玉」の真下に当たる部分、玉があれば絶対に見えない場所に、無数の細かい筋が見えた。
「指輪を加工したときに付いた傷ではありませんか?」
「私も最初はそのように思いましたが」
私はガイアの手からその古い指輪を受け取り、その一点に目を凝らした。
眩暈がするほど凝視した果てに、私はその筋が文字であることに気付いた。
髪の一筋よりも細い、寄り合わせる前の絹糸の一本よりも幽かな、しかしそれは確かな筆跡であり、文字であり、文章だった。
私が顔を上げると、ガイアは困惑した視線で、
「古い文字のようで、私には読めぬのですが、貴男になら判読できるのでは、と」
「博学なガイア・ファデッド卿が読めぬものを、この私が読めるとでも?」
「はい」
ガイアの視線から困惑が消え、澄んだ光が満ちた。
私は再び指輪に目を落とした。
確かに古い文字であった。
粗野で力強いクサビ跡のごとき斑文は、四百五十年昔までは確かに文字として通用していたが、今では読める者も少ない。
「『愚か者達よ
汝らの世界に審判の時が来た……』」
私の唇の僅かなふるえを、ガイアは驚嘆の眼差しで見た。
「やはり、レオン殿!」
「文字を読んでいる訳ではありませんよ」
「え?」
「かつて、ジン帝国時代以前の歴史を研究していた学者がこの文字に『擦紋文字』という呼び名を付け、翻訳を進めていました。……三十年以上昔の話です。
「三十年?」
「ところが、ギュネイ皇帝によりその研究は中止を命ぜられた。勅命ですから、学者は史料と研究内容を総て廃棄しなければならなかった。しかし、彼はある碑文の写しとその対訳のみは、捨てずに取っておいた。理由は判りませんが、おそらくは若い日に己が打ち込んだ情熱を、消し去ることが心苦しかったのでしょう。家族にすら知れない、一番安心できる場所にそれを隠していたのです。……好奇心旺盛な一人息子が、両親の寝室に飾られた絵画の裏張りを破がして見ることは、まるで予想できなかったようですが」
「その学者というのはもしや、かつてのハーン皇帝の御学友で、今ミッド大公家祐筆を勤める者のお父上に当たる方では?」
ガイアは笑った。寂しさも笑顔も苦痛も隠されていない本当の笑顔を、満面に浮かべた。
「彼の名誉のためにも、その悪戯な小倅のためにも、このことは口外無用に願います」
私が唇に人差し指をあてがいながら言うと、ガイアは無性に楽しいといった感の微笑みで同意を返してくれた。
「そのような次第で、私はこの文字を読める訳ではないのです。ただ、この文章はこういった意味であると、丸暗記しているに過ぎません」
「でも、意味が分かることは間違いない」
「そう言うことになります」
私は一つ息を吐き、暗記していた文字列を記憶の中から呼び出した。
「『愚か者達よ
汝らの世界に審判の時が来た
太陽と月と星の光は
崩れ往く物見の塔のように
悪しき者に魅入られている
戒めよ、死に向かいし者よ
つり下げられた者達よ
正義は運命の輪に組み込まれ
隠れ棲む者の力となる
戦場を駆ける馬車は
愛し合う者達を引き裂き
いと高き神の僕も
玉座のに坐す男も
権力ある女も
知識ある女も
魔術に翻弄され
木ぎれも剣も役には立たぬ
数多の金貨も聖杯の対価には足らぬ
やがて総てが無に帰るのであるから』」
これだけの長さの文章だが、擦紋文字なら僅か三十字足らずで表せる……と父の研究結果が主張している。線の数と組み合わせとによって、一つの文字で単語(時として文節)を表現できるのだ、と。
私は時折瞼を閉じ、天を仰ぎ、あるいは目を見開いて、うつむきながら、暗唱した。
その間ガイアは、目を細め、空を眺め、あるいは眼球を泳がせ、私の顔をのぞき込み、聞いていた。
「聞き流すと、意味が通っているようで、実は何の脈絡もない……」
同感である。
「恐らく俗謡の類でしょう。……そうでなければあるいは……」
「あるいは?」
「予言、占い、神託の断片である可能性も捨てられません。古代の、洗練されない宗教の覡(神官)が口述したものを、それなりの理由があって文字として残した……」
「碑文として残っており、また貴殿の家伝の品にもそれが彫り込まれているところからして、その説は有力ではある」
私はガイアの言葉に促されるように、再度古い指輪へ視線を移した。
祖母の遺品である。それはつまり、父が古代文字を研究する以前から、クミン家に存在していた物だということだ。……寝室の額縁の裏よりも安全な「秘密の隠し場所」として、父がそこの文字を刻みつけたという事象は考えづらい。
恐らく、かつては「それなりの理由」を持っていた文字列が、時経るごとに起源と理由を失い、呪いや護符の装飾として受け継がれてた、と私は考えた……のだが。
私は古びた金の表面の幽かな文字が震えるのを見た。己の目が原因かと、二,三度強い瞬きをしてみた。
ところが、目を開くたびに文字の震えは強くなる。やがて指輪そのものが激しく振動し始めた。
指輪は、それを押さえ込もうとする私の指先をはね除け、床に落ちた。震えながら病室の隅、私の手荷物がまとめ置かれている所まで床の上を滑り、止まった。
止まりはしたが、震えることはやめない。振動は益々大きくなり、ついには鼓膜を突き破りそうな鋭い金属製の高音を発っするに至った。
ガイアは残された左腕を自身の頭に巻き付け、何とか耳を塞ごうと足掻いている。
私はあわてて指輪に飛び付き、掌で覆い、床に押さえつけた。
勢いあまり、私は別途の脇に置いていた己の背嚢に体当たりを喰らわせる形となった。
倒れた背嚢の、甘く結わえられていた口が開き、荷物が溢れ出る。
大した荷物は入っていない。ガイアに付き添い泊まり込むために調達したその荷物と言えば、着替えと、数冊の書物と、僅かばかりの金子。
そして、赤い珠。
それは力学に則って、ぶつかった私から離れる方向に転がった。
途端、指輪の震えが一段と激しくなった。そればかりか、部屋の片隅に向かって転がっていた赤い珠までもが、直線的な動きを止め、小刻みに振動を始めたのである。
2つの物体が共振・共鳴し、空気の振動を超越した音波が私たちに襲いかかる。
思わず指輪から手を放し飛び退いた私は、ガイアに抱きつくと、彼女の右耳を自分の胸に押さえつけて塞ぎつつ、私自身の両耳を塞いだ。
競うように金切り声をあげていた二つの物体だったが、徐々に「優劣」が現れ始めた。
赤い珠が大きく揺れ、指輪は小さく揺れる。
赤い珠の大きな揺れは力つきる直前の独楽よろしく、あやふやで心許ない。
指輪の小さな揺れは羽虫の羽ばたきに似て、鋭く正確な振幅を続けている。
そうして2つの揺れは、私たちのちっぽけな常識では思いも寄らない現象を引き起こした。
赤い珠が、指輪に引き寄せられてゆく。
引き寄せられながら、圧縮されてゆく。
圧縮され、引き寄せられたそれが、指輪の元にたどり着いたとき、握り拳ほどであった珠は、小指の先ほどの粒になり果てていた。
それは、ちょうど指輪の縦爪にはまるほどの大きさだった。そして実際にその珠は指輪にぴったりと填り込んだ。
一体となった2つの物は、その瞬間からぴたりと震えるのを止めた。
不愉快な音が消え、水を打った静けさが重く広がった。
「一体、何が起きたのだ……?」
ガイアは素直な疑問を素直なままに口にした。
私はただ頭を振った。混乱する頭を、混乱の侭に。
ガイアにも私の混乱がすぐに判ったようだ。漠然過ぎた質問に筋道を立ててくれた。
「あの赤い珠は?」
「クォイティエ代官レイモンド・ノギア……。魔物に変じた後、命を失ったノギアが、最後に残した彼自身の痕跡……。恐らく【アーム】と総称される物体の一つ」
私は言いながら、脳の中で私が経験した事象を整頓していた。
「一つ?」
「そう呼ばれる物が複数存在すると思われますので」
経験の整頓から推察に転じた私の脳漿は、ある一つの推理にたどり着いた。
……太古から【アーム】なる物は存在していた。
……その危険性を、太古の者は知っていた。
……彼らは危険性を弱める方法を考え、ついに【アーム】を封印する呪文にたどり着いた。
……それを刻んだ呪符の影響下にある限り【アーム】の力は封じられ、小さな枠の中に押し込められる。
……そしてあるときその方法が実行され、呪文を刻んだ指輪型の呪符に、一つの【アーム】が封印された。
……赤珊瑚珠の指輪さながらの形に納められたそれをクミン家の祖先が手に入れ、子孫へ伝えられた。
……その子孫の果てが、それの危険性を知らぬ侭にそれを扱った。
私自身が導き出した結論に、私は全身が革ひもで締め付けられるかのような苦しみを感じていた。
ガイアを危険な目に遭わせ、傷付け、左腕を失わせた、その原因を作ったのは、この私ではないか!
愚かな私の無知の故に、彼女は命を脅かされたのだ!
「それは、違う」
ガイアが低く澄んだ声でつぶやいた。
「何が、違うと?」
私は険のある声音で尋ね返した。
自信があったのだ、己の推論に。己の愚かさに。それを彼女が否定したことが、癪に障った。
ガイアは静かに微笑んだ。そして私の問いには答えずに、さらなる疑問を投げかけた。
「あの珠が指輪から外れたのは、何故でしょう?」
「それは……。呪符の力が弱まって……」
「呪符の力が落ちていたとは考えられません。なにしろ、たった今それによって別の【アーム】が封印されたのですからね」
確かにそうだ。
私は張り子の虎の様に無様にうなずいた。
するとガイアは、圧倒的な理論展開を始めた。
「静止する物体は、外部から力を加えられぬ限り静止し続ける……と、力学の学者が言っていた。この法則を【アーム】に当てはめてはなりませんか?」
私は呆けた相づちを打つ。
「あの【アーム】は、件の呪文のよってこの指輪に止められていた。指輪から外れるためには、外から力が加えられねばならない。
……ここで言う力とは、力学的な意味での力ではない。【アーム】を止めている『力』が力学用語の『力』とは違うのように、それをはずす『力』も力学の『力』ではない。
件の呪文が持つ説明のしようがない力、それに対応しうる説明しようのない別の力が外部から加わったために、珠は外れた。
外れたことによって珠は元の力を取り戻し、その力を発揮できる身体を求めた。その場に、ちょうど良い按配に私がいた。
そして、その加えられた力の元は……恐らく私自身」
ガイアは一つ吐息を挟んで付け足した。
「私にはそんな『力』を発した自覚が、まるでないのだけれど」
長いことほどけなかった靴ひもがようやっとほどけたといった、清々しい表情で彼女は「己が原因」と断言した。
私は彼女の理論に依存を唱えなかった。
彼女にそんな「力」があったとしても、なんの不思議も感じられない。むしろ、そのような力にあふれた人物だと思える。
なんといっても、私自身が一番強くその力に影響されていることを感じているのだから。
-了-

【メニューへ】