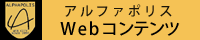レオン・クミン記《一》
ミッド大公ハーン家祐筆 レオン・クミンによる回述
二重の喜びだった。
己の話に、興味を持ってくれる人物がいたこと。
そしてその人物が、その女性であったこと。
「姫様へ語る、お伽噺のネタ仕入れですか?」
試みに、問うてみた。
その女性……クレール=ハーン姫付き侍女、教育係にして学友……ガイア・ファデッド嬢は、気恥ずかしそうに微笑んで、首を横に振った。
「純粋に自身の興味から、ですよ、クミン殿」
輝いていた。
近衛兵の着る真紅のジャケットを羽織り、折り目正しいプリーツがゆったりと重なった濃紫の丈長なキュロットをはいたその姿も、日に灼けた頬に浮かぶ凛々しい微笑も、全てが我が目に眩しかった。
ここは、何事も控えめ……地味ともいうが……な我が故郷ミッド公国で、唯一「壮麗なサロン」と呼んでもよい場所だ。
とはいうものの。
確かに、貴族達、金持ち達が主な客だが、普通の臣民も慶事には多々利用するから、他の「大国」から見れば、単なる「レストラン」に過ぎぬだろう。
しかし、私は嬉しかった。
ここにファデッド嬢と向かい合って居、共に食事を摂っていること、それ自体が至福だった。
「……クミン殿?」
ファデット嬢が、私の目を覗き込み、不安げな声を出した。
「聞いて、おられるか?」
「無論!」
私は精一杯の笑顔を浮かべた。
きっと、普段は青白い頬が、炎のように赤くなっていたに違いない。
「私は、嬉しいのですよ、ファデッド嬢。私は……」
「クミン殿、嬢は、止めていただきたい」
ファデッド嬢は、照れた笑みを浮かべ、掌を大きく左右に振った。
「そのようには、呼ばれ馴れていないのですよ。それに、私は貴殿より年下、それに爵位も……。ですから、ガイアと呼び捨ててくださって結構」
息を呑んだ。半信半疑とはこのことだ。
こんな光栄なことが、我が身に起こって良いのだろうか?
呼び捨ててよい? それも、ファーストネームで!?
私は、持てる勇気の全てを振り絞って、それでも恐る恐る言った。
「で……では、ガイア……」
「はい」
ファデッド嬢……いや、ガイアは、満面の笑みでうなずいてくれた。
私は一瞬、気を失うのではないかと思った。
笑わないでいただきたい。私には、それほどに幸福な瞬間だったのだ。
私は深呼吸を一つすると、努めて冷静に、ガイアに訊ねた。
「何からお話しすれば良いのでしょう?」
ガイアは、わずかに小首を捻った後、ゆっくりとした口調で答えた。
「最初から。そう、今日の昼下がり、お茶の時間に、貴殿が姫若様と私とに語ってくれた話から。そして叶うことなら、貴殿がその時語ってくれなかったことを、全て」

そう。
この日の昼下がり、私は、クラウンプリンセス・クレール姫の三時のお茶のご相伴に預かる幸運を得た。
予定されていた大公ジオ三世殿下ご臨席の会議が、司空(建設大臣)殿の急な病で中止となり、時間が空いたのが……司空殿には気の毒ではあるが……幸いしたのだ。
ご利発で、何事にも興味を示される、少々御転婆なクレール姫は、親友とも呼んでよいであろう学友であるガイアと、二人きりで歓談するおやつの時間に、このところ少々飽きておられたらしい。
強く男子を欲しておられていた大公殿下は、この姫君を若君の如くお育てになられた。
これをして、「姫のような若君だ」などと事実に反することを言い、「姫若」などと呼ばわる愚か者がいた。どちらかといえば「若のような姫君」であるから「若姫」が正当であろうが、当のクレール姫は何故か前者の呼ばれ方をお気に召しておられるようだ。
それは兎も角も。
ありきたりの少女であれば甘い菓子とお茶だけで数時間は時を過ごすことができるにもかかわらず、姫はそういった穏やかな時間の使い方が苦手であられる。
姫様はいつも彼女に、「お話」をせがまれる。
それも毎日違う物語を、だ。
しかし、いくら博学とはいうものの、まだ年若いガイア……実はまだ十五歳で、姫様とは五つほどしか違わないのだ……が知る「うわさ話」「お伽噺」「昔話」「寓話」「冒険譚」には限りがある。
新しい話題を求められる姫様の哀願に、彼女が困り果てて辺りを見回した、丁度その視線の中に、暇を得た私の姿が映ったのだ。
運が良かった。……ガイアにとっても、私にとっても……。
小さな国の主の城、というか領主の屋敷というか……の、猫の額ほどの美しい中庭に設けられた、小さな丸テーブルでのささやかなお茶会だった。
「とても不思議なお話です。……少々恐いお話になるかも知れませんが、それでもよろしいでしょうか?」
私は精一杯の笑みを向けた。
正直な話だが、私は笑うのが少々苦手なのだ。
いや、自分では笑っているつもりなのだが、生来の顔色の悪さが、「つもり」を他人には知らせてくれないようなのだ。
しかし今回は巧く笑顔を作れたらしい。
クレール姫様は、嬉しそうに大きくうなずかれた。
「恐いお話は大好き。ねぇ、ガイア?」
同意を求められたガイアは、少し困惑気味ではあったが、首を縦に振った。
「解りました。……では、恐くてもう聞きたくないと思われたら『もう止めなさい!』と、ご命令下さい」
そう前置きして、私はこんな「物語」を語った。

男の子が居りました。小さな男の子です。
体が弱く、よく病気をしていたので、ずっと長いことある病院に入院していました。
ある天気の良い日、男の子は同じ部屋で眠っている、お年寄りの病人の頭の上に、何かが乗っているのに気が付きました。
それはまるで、高い山のてっぺんに懸かる、丸い雲のような物でした。
雷雲のように少し黒みがかったそれは、お年寄りが起きても、食事をしても、お手洗いに立っても、そしてまたベッドに戻っても、ずっと頭の上に乗り続けています。
初め男の子は、自分の目がおかしくなったのだと思いました。
少し前に、ぼんやり目が霞む病気にも罹ったことがあったので、またその病気が顔を出したのだと、そう考えたのです。
その晩のことです。
真夜中、そのお年寄りが急に苦しみ始めました。
お医者さまは慌てて飛び起きて、一生懸命介抱しましたが……とうとう、お年寄りは助かりませんでした。
次の日の朝のことです。
男の子は、隣の病室に入院している小さな女の子の怪我人が、病院の庭で日向ぼっこをしているのを見かけました。
そして、その女の子の頭の上に、何かが乗っているのに気が付きました。
それはまるで、高い山のてっぺんに懸かる、丸い雲のような物でした。
秋の鰯雲のように真っ白なそれは、女の子が歩いても、絵本を読んでも、看護婦さんとお話をしていても、ずっと頭の上に乗り続けています。
夜が来て、朝が来て、お昼が過ぎました。
男の子がベッドの上で横になっていると、隣の病室から、泣き声が小さく聞こえてきました。
怪我をして入院をしていた、小さな女の子の、お母さんの泣き声です。
「ああ、娘よ。たった一人の娘よ! なんでお母さんよりも先に死んでしまったの!?」
少し前に手術をし、しっかりと縫い合わせた、そしてもうじきふさがるはずだった傷口が、何かの拍子にパックリと開いて、急に血がたくさん出てしまい、それが元で、あの小さな女の子は死んでしまったのです。
夜が来て、また朝が来ました。
病院のドアを叩く大きな音で、みんなが目を覚ましました。
「急患です、急患です! 先生、人足が荷車の下敷きになりました! お願いです、診てください!」
男の子は病室のドアを少しだけ開け、その隙間から、病院の入り口の方をのぞき見ました。
戸板の上に乗せられた、血まみれの男の人は、どんよりとした真っ黒な雲に包まれています。
お医者さまが、力無く首をふりました。
「もう手遅れです」
男の人の仲間や友達や家族が、わぁわぁと泣き出しました。
男の子はドアを閉め、自分のベッドに飛び込みました。
実は、もう一つ雲が見えていたのです。
あの血まみれの男の人を包んでいたのとは違う雲です。
それは、男の人の家族……たぶん、奥さんか恋人でしょう……の頭の上に乗っていました。
白い雲でした。輝くような白い雲でした。
……数日後、男の子はうわさ話を聞きました。
「博打とお酒と喧嘩が大好きで、悪いことをたくさんしたことのある荷揚げ人足のことを、それでも大好きだった優しい娘さんが、その人足が事故で死んだのがショックで、病気になって死んでしまった」
男の子は恐くなりました。
身体が、ガタガタと震えました。
「僕が頭の上に『雲』を見た人は、全員死んでしまった!」
一日中、毛布を頭までかぶり、ご飯も食べないで、泣いていました。
それでも、しばらく後には、男の子の病気はだいぶ良くなり、退院することになりました。
男の子は下を向いたまま病室を出、下を向いたまま廊下を歩き、下を向いたままお医者様に挨拶をし、下を向いたまま外に出ました。
見えるのです。
何人かの患者さんの頭の上に、黒っぽいのや白っぽい雲が漂っているのが。
見えるのです。
外を歩く人々の中にも、黒っぽいのや白っぽい雲を、頭上にたなびかせている人達が何人も。
見えるのです。
親戚の人や、おうちの近所の人や、知っている人達の中にも、黒っぽいのや白っぽい雲を担いでいる人のいるのが。
そうして、そんな人達が全て、しばらくたつと死んでしまうのです。
「死神だ」
男の子は思いました。
「僕には死神が見えるのだ」
男の子は、一生懸命「雲が見えること」と、「雲が見えた人はもうじき死んでしまうのだ」ということに馴れようとしました。
何年もかかって、ようやく馴れることはできました。
しかし、馴れてからは、もっと辛くなりました。
大好きな人、大切な人、尊敬する人、そんな人達の頭の上に雲が乗っていても、その雲を追い払うことができないからです。
忠告することはできます。
ですが、誰も信用してくれません。
信じてくれたとしても、その雲が消えることはありませんでした。
我慢するしかないのです。
例え、あなたの頭に雲がかかっているのが見えたとしても……。

私は最後の一言を言いながら、クレール姫様の頭の上あたりを指さした。
と。
「きゃぁー!」
日ごろお勇ましい姫若様が頭を抱え、テーブルに突っ伏し、ブルブルと震えながら、
「見えるの? 私の頭に、雲があるの!?」
と、エメラルドの目から大粒の涙をこぼされたのだ。
「見えません」
私は答えた。できる限り、優しい顔をしたつもりだった。
姫様は、そぉっと顔を上げ、私を睨み付けると、
「真面目なレオンがこんなに不気味で恐ろしい話をするなんて、思っても見なかった。でも、とても面白かったから、許します」
涙を拭いながら、にっこり笑い、お褒め下さった。
その時、ガイアは苦笑いをしていた。
楽しそうな、苦笑いだった。
「あの物語、実は『作り話』ではないのでしょう?」
食前酒のグラスを揺らしながら、ガイアが私を見つめた。
「あれは貴殿自身の身に起こる事象。実際に貴殿には……『死神』が見える……違いますか?」
真剣な眼差しだった。
私は、うなずいた。
「貴女に信じていただけるとは、思ってもいませんでした。何分、貴女というヒトは、頭が良い上に、実力主義・現実主義な方だと思っておりましたから」
「貴殿にそう評して頂けたことは、実に喜ばしい。……事実、私は実力主義・現実主義を信条にしています。……だからこそ、貴殿の『能力』に興味がある」
「『能力』……と言われるか? この不可思議な現象を?」
ガイアは真剣な瞳で、しかし、口元には笑みを浮かべて、こう言った。
「目が見える。匂いを嗅げる。耳が聞こえる。味を感じる。物に触れる。あるいは、喋る、歩く、走る。……誰しも当たり前に取る行動だ。しかし、盲目の者にとっては、見るということ自体が『特殊な能力』に思えることでしょう。嗅覚をなくした者には、薔薇の香りをかぐこと自体が『己には感じ得ない感覚』となりましょう。聾唖の者、身体が麻痺した者、四肢を失った者には、音も、触感も、歩くことも、『自分にはできない能力』となる……違いましょうか?」
私は驚いていた。
細い目を見開き、口をポカンと開けた、相当にしまりのない顔をしていたことだろう。
本当に、私は驚いていた。
ガイア・ファデッドという女性の聡明さに、その英智の深さに。
そして、自身の感情に呆れていた。
この、世間から「男女」だの「おんな女形」などと呼ばれる女性に、一目会ったその日から恋心を抱いた、己の洞察力の深さに。