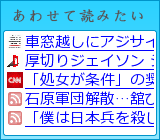【ご注意】
この日記もどきは長期間書き続けられておりますため、過去ログ記事中にはリンク切れが多数発生しております。
なにとぞご容赦下さいませ。
この日記もどきは長期間書き続けられておりますため、過去ログ記事中にはリンク切れが多数発生しております。
なにとぞご容赦下さいませ。
••• category •••
2009年10月22日(木)付記事が何となく人気っぽいので、独立したファイルにしてみる。
| 日本合戦譚 真田幸村 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 第一次上田合戦から、小田原の役、関ヶ原の役(第二次上田合戦)、九度山流配までをざっとおさらい。 大阪の役での真田信繁について書く。 (2009/10/30(Fri) 14:49) | |
| 日本合戦譚 山崎合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 山崎の戦いは、天正10年(1582年)6月に本能寺の変で織田信長を討った明智光秀に対して、備中高松城の攻城戦から引き返してきた羽柴秀吉が、6月13日(西暦7月2日)京都へ向かう途中の摂津国と山城国の境に位置する山崎(大阪府三島郡島本町山崎、京都府乙訓郡大山崎町)で、明智軍と激突した戦い。 「天王山の戦い」とも呼ばれる。 秀吉が、いわゆる「中国大返し」といわれる機敏さで畿内へ急行した事で有名。 (2009/10/30(Fri) 14:40) | |
| 日本合戦譚 碧蹄館の戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 碧蹄館の戦い(へきていかんのたたかい)は、文禄・慶長の役(日本と明との間で行われた戦争:唐入り、朝鮮出兵)における合戦の一つ。 文禄2年(1593年)1月26日に朝鮮半島の碧蹄館(現在の高陽市徳陽区碧蹄洞一帯)周辺で、平壌奪還の勢いに乗り漢城(現在のソウル)めざして南下する提督李如松率いる40,000余の明軍を、宇喜多秀家、小早川隆景らが率いる約41,000の日本勢が迎撃し打ち破った戦い。 明・朝鮮側は、この戦いの敗北によって李如松が戦意を喪失。勢いはそがれ、以降戦線は膠着状態となった。 その一方で日本軍も3月に明軍に漢城近郊・龍山の兵糧倉を焼き払われ、兵糧面で甚大な損失を出したため長期戦が難しくなり、石田三成、小西行長らは明との講和交渉をはじめることを余儀なくされる。 (2009/10/30(Fri) 14:37) | |
| 日本合戦譚 賤ヶ岳合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 賤ヶ岳の戦いとは天正11年(1583年)、近江国伊香郡(現:滋賀県伊香郡)の賤ヶ岳附近で行われた羽柴秀吉(豊臣秀吉)と柴田勝家との戦い。 秀吉方で功名をあげた兵のうち以下の7人は後世に賤ヶ岳の七本槍と呼ばれる。 七本槍のメンバーは以下の通り。 福島正則(1561年 - 1624年)/加藤清正(1562年 - 1611年)/加藤嘉明(1563年 - 1631年)/脇坂安治(1554年 - 1626年)/平野長泰(1559年 - 1628年)/糟屋武則(1562年 - 1607年) なお7人と言うのは後の語呂合わせで、譜代の有力な家臣をもたなかった秀吉が自分の子飼いを過大に喧伝した物であるとも言われる。 (2009/10/30(Fri) 14:27) | |
| 日本合戦譚 長篠合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 長篠の戦いは、天正3年5月21日(1575年6月29日)、三河国長篠城(現愛知県新城市長篠)をめぐり、織田信長・徳川家康連合軍3万8000と武田勝頼軍1万5000との間で行われた戦い。 決戦地が設楽原および有海原だったため「長篠設楽ヶ原の戦い」と記す場合もある。 異論はあるが、通説では、当時最新兵器であった鉄砲を3000丁も用意、さらに新戦法の三段撃ちを実行した織田軍を前に、当時最強と呼ばれた武田の騎馬隊は成すすべも無く殲滅させられたとされる。 (2009/10/30(Fri) 14:08) | |
| 日本合戦譚 田原坂合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 西南戦争(西南の役)は1877年(明治10年)に現在の熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県において西郷隆盛を盟主にして起こった士族による武力反乱である。 田原坂の戦いはその中で、3月1日から3月31日まで、田原坂・吉次峠(現在の熊本県鹿本郡植木町大字豊岡)で繰り広げられた激戦のこと。 田原坂は、標高差わずか80mに、一の坂、二の坂、三の坂と頂まで1.5kmの曲がりくねった道が続く場所。 ここ以外には大砲をひいて通れる幅(3〜4m)の道がないため、熊本目指す官軍の砲兵隊はここを進まざるを得ない。 すなわち西郷軍に取っては絶対に落とせない防衛ラインということである。 この両軍にとって戦略上の重要地で、一日の弾丸使用量は32万発という壮絶な戦いが17昼夜にわたって繰り広げられた。(2009/10/30(Fri) 14:05) | |
| 日本合戦譚 桶狭間合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 桶狭間の戦いは、永禄3年5月19日(1560年6月12日)に今川義元と織田信長との間で尾張国桶狭間で行われた合戦。 2万5千の大軍を引き連れて尾張に侵攻した駿河の戦国大名・今川義元に対し、尾張の大名・織田信長が10分の1程の軍勢で本陣を強襲し、今川義元を討ち取って今川軍を潰走させた、日本の歴史上最も華々しい逆転劇と言われている、非常に有名な戦い。 今川軍は様々な方面に戦力を分散させており、義元を守る本隊は5,000〜6,000人ほどに過ぎなかった。更にその大部分は戦闘に不慣れな寄せ集めの兵であった。そのため、精鋭2,000人が一丸となって突撃してきた織田軍の猛攻によって大混乱に陥いり、乱戦となった。 義元の戦死により今川軍本隊は壊滅し、合戦は織田軍の大勝に終わる。 (2009/10/30(Fri) 13:46) | |
| 日本合戦譚 川中島合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 川中島の戦いは、戦国時代に、甲斐国の戦国大名である武田信玄と越後国の戦国大名である上杉謙信との間で、北信濃の支配権を巡って行われた何回か(五回とするのが現在の通説)の戦争の総称。 最大の激戦となった第四次の戦いが千曲川と犀川が合流する三角状の平坦地である「川中島(長野県長野市南郊)」を中心に行われたことから、その他の場所で行われた戦いも総して「川中島の戦い」と呼ばれる。 実際に「川中島」で戦闘が行われたのは、第二次(犀川の戦い)と第四次(八幡原の戦い)のみ。 一般に「川中島の戦い」と言った場合、最大の激戦であった第四次合戦(永禄4年9月9日(1561年10月17日)〜10日(18日))を指すことが多い。 (2009/10/30(Fri) 10:09) | |
| 日本合戦譚 厳島合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 厳島の戦いは、天文24年10月1日(1555年10月16日)に、安芸国厳島で毛利元就と 晴賢は天文20年(1551年)に主君であった大内義隆を討つクーデターを成功させ、傀儡とも言える新君主・大内義長を立てることによって大内家の実権を握っていた。 徹底した軍備強化を行なった晴賢に対して反発する傘下の領主も多かった。やがてそれは先主・義隆の姉婿である吉見正頼や、毛利元就の反攻を招く。 厳島合戦の結果、大内氏は急速に弱体化し、かわって毛利氏がその旧領を併合していくことになる。 (2009/10/30(Fri) 09:59) | |
| 日本合戦譚 姉川合戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 姉川の戦いは、戦国時代の元亀元年6月28日(1570年8月9日)(ユリウス暦1570年7月30日)に近江国浅井郡姉川河原(現在の滋賀県長浜市野村町(旧:東浅井郡浅井町野村 域)付近)で行われた合戦。 当時は織田、浅井方ともこの合戦を「野村合戦」と、朝倉方では「三田村合戦」と呼称していた。 「姉川の合戦」は徳川家における呼称。 『信長公記』などに合戦の記述があるが、簡潔な内容にとどまる資料が多く、合戦の詳細については不明な部分が多い。 (2009/10/30(Fri) 09:44) |
やる夫が真田家に生まれたようです
http://ansokuwww.blog50.fc2.com/blog-entry-257.html
↑は更新が止まっている模様。
↓コッチは生きてる模様。
http://gnusoku.blog41.fc2.com/blog-entry-405.html
http://ansokuwww.blog50.fc2.com/blog-entry-257.html
↑は更新が止まっている模様。
↓コッチは生きてる模様。
http://gnusoku.blog41.fc2.com/blog-entry-405.html
敬称略で。
大阪夏の陣(慶長20年4月26日開戦)直前に送られた書状で、
Web上の有名人の「辞世の句/最期の言葉」系のサイトで「幸村の最期の言葉」として上げられることの多い
さだめなき浮世にて候へ者、一日先は知らざる事、我々事などは浮世にあるものとは、おぼしめし候まじく候
の原文。
「真左衛門佐」は真田左衛門佐の略。左衛門佐は信繁の官位。
「小壱岐様」は小山田壱岐守の略で、真田信之の家臣(次席家老)である小山田茂誠(重誠)のこと。
茂誠は真田昌幸の長女お国(村松殿/宝寿院)の夫で、信之・信繁兄弟の義理の兄に当たる。
「主膳殿」はその子の小山田之知のこと。
以下現代語訳。間違ってたらごめんなさい。
遠路預御使札候、其元相替儀無之由、具承、致満足候、爰元おゐても無事ニ候、可御心安候、我等身上之儀、殿様御懇比も大かたの事ニはハ無之候へとも、萬気遣のみニて御座候、一日一日とくらし申候、面上ニならて委不得申候間、中々書中不具候、様子御使可申候、当年中も静ニ御座候者、何とそ仕、以面申承度存候、御床敷事山々ニて候、さためなき浮世ニて候へ者、一日さきハ不知こと候、我々事なとハ浮世にあるものとハおほしめし候ましく候、恐々謹言
三月拾日 真左衛門佐
小壱岐様
同主膳殿 信繁(花押)
御報
尚々、別帋ニ可申入候へとも、指儀無之候、又御使如存候、少用取乱申候、早々如此候、何も追而具申入候、以上
大阪夏の陣(慶長20年4月26日開戦)直前に送られた書状で、
Web上の有名人の「辞世の句/最期の言葉」系のサイトで「幸村の最期の言葉」として上げられることの多い
さだめなき浮世にて候へ者、一日先は知らざる事、我々事などは浮世にあるものとは、おぼしめし候まじく候
の原文。
「真左衛門佐」は真田左衛門佐の略。左衛門佐は信繁の官位。
「小壱岐様」は小山田壱岐守の略で、真田信之の家臣(次席家老)である小山田茂誠(重誠)のこと。
茂誠は真田昌幸の長女お国(村松殿/宝寿院)の夫で、信之・信繁兄弟の義理の兄に当たる。
「主膳殿」はその子の小山田之知のこと。
以下現代語訳。間違ってたらごめんなさい。
遠いところを御使者をお送り下さりありがとうございます。
そちらはお変わりがないとのこと、詳しく承り、満足いたしました。
こちらにおきましても無事でございますので、ご安心下さい。
私たちの身の上のことについてですが、お殿様(豊臣秀頼)は大変親切にしてくださるので大抵のことは問題ないのですが、色々と気遣いしながら、一日一日生活しています。
お会いしなくては細かいところを申し上げることはできません。手紙では中々詳しく書けませんが、御使者の方が詳しく伝えてくださるでしょう。
今年も何事もなければ、どうにか、お目にかかりたいと思っています。知りたいことが山ほどあるのです。
ですが、この不安定な世情のことですから、明日のこともわかりません。私たちのことなどはもうこの世にはいないものだとお考え下さい。
恐れながら謹んで申し上げます。
署名
なお、本来はお二人別々に書状をお送りするべきなのですが、それほど重要なことでもございませんし、また御使者もご存じの如く、少々取り乱れておりますので、急ぎこのようにしました。
何れ追って詳しいことをお知らせいたします。
以上。
 だいすき!戦国武将〜よくわかる 気になる主従の萌えどころ〜
だいすき!戦国武将〜よくわかる 気になる主従の萌えどころ〜戦武連 (著), ブレインナビ (編集), 前田 浩孝 (イラスト), kasumi (イラスト), 鳥海 三保子 (イラスト), みむら六 (イラスト), 柳けふ (イラスト), ユガヲ (イラスト), 吉村 正 (イラスト)
出版社: 廣済堂出版 (2009/10/16)
若い女性を中心にブームの「戦国武将」キャラクターを絢爛なイケメンイラストで紹介。
萌えるエピソード満載のビジュアル歴史ブック。
(2009/10/04(Sun) 20:11)
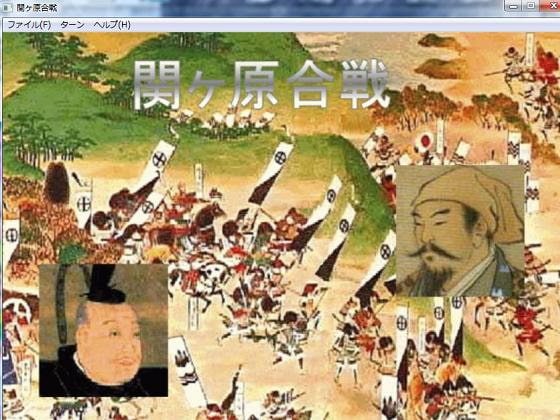
関ヶ原合戦
::サークル名 AlphaStrike
::登録年月日 2009年09月27日
::作品内容
このゲームは慶長5年(1600年)9月15日、美濃の関ヶ原を舞台にして行われた天下分け目の関ヶ原合戦をシミュレートしたゲームです。
プレイヤーはそれぞれ、徳川家康率いる東軍と、石田三成率いる西軍とに分かれそれぞれの勝利条件を達成することを目的とします。
::年齢指定 一般向け
::作品形式 同人ゲームシミュレーションゲーム
::ファイル形式 アプリケーション
::対応OS WindowsXP / WindowsVista
::ファイル名/サイズ RJ053883.zip / 2187428 Byte (2.09 Mbyte)
::その他 3D作品
必須動作環境
::DirectX 9.0c
価格(税込み) 105円
| LOG | 2007 | 05 06 07 09 10 11 12 |
| 2008 | 01 05 06 08 09 10 11 12 | |
| 2009 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2010 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 | |
| 2011 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2013 | 01 02 03 04 06 07 08 10 11 | |
| 2014 | 02 05 06 08 12 | |
| 2015 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2016 | 01 02 03 05 06 09 10 12 | |
| 2017 | 01 02 03 10 11 12 | |
| 2018 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 | |
| 2019 | 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 | |
| 2020 | 02 04 05 06 07 09 12 | |
| 2021 | 01 02 04 05 06 07 08 10 | |
| 2022 | 01 03 04 05 06 08 12 | |
| 2023 | 01 04 05 06 07 08 | |
| 2024 | 11 |
••• 日記内検索 •••
recent entries
••• calendar •••
••• Contact •••
••• Ranking •••
••• About Us •••
••• Amazon.jp •••
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
Thanks
••• thanks •••
Nicky!: diary CGI
Shi-dow: shi-painter
WonderCatStudio: dynamic palette
Promised Land: skin
非公式マニュアル : tips
賑町: icons
RSSアイコン:RSSicon
さくらインターネット :hosting
:hosting
Shi-dow: shi-painter
WonderCatStudio: dynamic palette
Promised Land: skin
非公式マニュアル : tips
賑町: icons
RSSアイコン:RSSicon
さくらインターネット
Caretaker Only