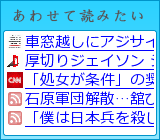【ご注意】
この日記もどきは長期間書き続けられておりますため、過去ログ記事中にはリンク切れが多数発生しております。
なにとぞご容赦下さいませ。
この日記もどきは長期間書き続けられておりますため、過去ログ記事中にはリンク切れが多数発生しております。
なにとぞご容赦下さいませ。
••• category •••
| 日本合戦譚 四条畷の戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 四條畷の戦い(しじょうなわてのたたかい)は、南北朝時代の1348年(正平3年/貞和4年)1月5日、河内国北條(現在の大阪府四條畷市・大東市)における、南朝方の楠木正行と足利尊氏の腹心である高師直との間の戦い。 楠木正行は本拠地である河内国南部から、摂津国南部の住吉・天王寺周辺までゲリラ的に出没。足利方を脅かしていた。 1347年(正平2年/貞和3年)9月、楠木軍は藤井寺近辺で細川顕氏を破り、11月には住吉付近で山名時氏を破る。 足利方は本格的な南朝攻撃を決意。 1348年1月に高師直を大将とする大軍を編成して、北上する楠木軍と四條畷に対峙した。 楠木軍は足利方の圧倒的な兵力の前に敗北。正行は弟の正時と刺し違えて自決。 勢いに乗った高師直は、南朝の本拠吉野(奈良県吉野郡吉野町)に攻め入り陥落させる。 後村上天皇はじめ南朝は賀名生(同県五條市)に逃れた。 (2009/12/29(Tue) 17:43) | |
| 日本合戦譚 島原の乱 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 島原の乱は、寛永14年10月25日(1637年12月11日)に勃発、寛永15年2月28日(1638年4月12日)終結した「キリシタン一揆」。島原・天草一揆、島原・天草の乱とも呼ばれる。 一般的に宗教弾圧による戦争と認識されているが、実質は、島原藩・唐津藩による圧政に苦しんだ農民などの諸領民による反乱であった。 年貢の過酷な取り立てや、切支丹への残忍な拷問・処刑に耐えかねた島原の領民は、旧有馬氏の家臣の下に組織化。密かに反乱計画を立てていた。同じ頃、肥後天草でも、大量に発生した浪人を中心に一揆が組織されていた。 両一揆の首謀者たちは湯島(談合島)において会談を行う。 そしてキリシタンの間でカリスマ的な人気を得ていた当時16歳の少年・天草四郎(益田四郎時貞)を一揆軍の総大将に立てて、決起することを決定。 寛永14年10月25日(1637年12月11日)、有馬村のキリシタンが中心となって代官・林兵左衛門を殺害。ここに島原の乱が勃発する。 島原藩は直ちに討伐軍を繰り出し一揆軍を迎撃するが敗走。 この戦闘に呼応して、数日後に肥後天草でも一揆が蜂起。11月14日に富岡城代を討ち取った。 一揆軍は唐津藩兵が篭る富岡城を攻撃。落城寸前まで追い詰めるも、九州諸藩から討伐軍に背後を突かれることを嫌って撤退。 一揆勢は島原半島に移動し原城址に篭城。ここで合流した島原と天草の一揆勢は37,000人程(27,000人との異説有)。 原城を包囲した討伐軍は12月10日、20日に総攻撃を行うが敗走。 翌年1月1日(1638年2月14日)に再度総攻撃を行うが失敗。死傷者4,000人以上の損害を出す。 しかし増援を得た討伐軍は12万以上の軍勢に。原城の兵糧が少ないと見ると、兵糧攻めに作戦を切り替える。 討伐軍は2月28日に総攻撃を決定。鍋島藩勢が予定の前日に総攻撃を開始する。 この総攻撃で原城は落城。天草四郎は討ち取られ、乱は鎮圧された。 幕府軍の攻撃とその後の処刑によって一揆側の死者は37,000人(つまり全滅)。 13万近くを動員した幕府討伐軍側は、一説に8,135人の死者を出したという。 (2009/12/29(Tue) 17:37) | |
| 日本合戦譚 鳥羽伏見の戦 | |
| 作家名:菊池寛(池島信平の下書きに基づくとも) 戦国時代から明治まで、歴史の転換点となった日本の代表的な合戦を活写した歴史随想集「日本合戦譚」収録の一遍。 鳥羽・伏見の戦い(慶応4年1月3日-6日(1868年1月27日-30日))は、京都南郊の上鳥羽(京都市南区)、下鳥羽、竹田、伏見(京都市伏見区)で行われた戦闘。戊辰戦争の緒戦となった。 慶応3年末に発せられた王政復古の大号令により、前将軍・徳川慶喜に対し辞官納地が命ぜられた。 慶喜は新政府(明治政府)に恭順の意思を示すため、12月13日、京都の二条城を出て大坂城へ退去するも、その後、政府への連絡が途絶える。 12月25日(1868年1月19日)、薩摩藩が江戸市街で挑発的な破壊工作を行うと、慶喜の周囲で「討薩」を望む声が高まり、慶喜は薩摩征伐を名目に事実上京都封鎖を目的とした出兵を開始。幕府歩兵隊は鳥羽街道を進み、会津藩、桑名藩の藩兵、新選組などは伏見市街へ進んだ。 慶応4年正月3日(1868年1月27日)夕方、下鳥羽付近で街道を封鎖する薩摩藩兵と旧幕府軍戸の間に軍事的衝突が起こる。鳥羽での銃声が聞こえると伏見でも衝突が起き、こうして戦端が開かれることとなった。 5日、明治天皇が仁和寺宮嘉彰親王に錦旗(錦の御旗)を与えた。(岩倉具視による偽造説も)こうして新政府軍は「官軍」となる。 旧幕府方は立て直しを図ろうと淀城に行くが、淀藩は入城を拒否。仕方なく淀千両松に布陣し、政府軍を迎撃した幕府軍だが、惨敗を喫する。 さらに津藩が新政府側へ寝返るなどしたため、戦意を喪失した旧幕府軍は総崩れとなる。 7日に慶喜に対して追討令が出た報を聞くと、大阪城にいた慶喜は密かに城を脱し、8日には開陽丸で江戸に退却した。 政府軍の砲兵力を見せつけられ、また総大将が退却したことから、多くの藩が旧幕府軍を見限った。 旧幕府方は当初15,000人の兵力を擁しながら、5,000人の新政府軍に敗れたのだった。 (2009/12/29(Tue) 16:31) |
曹操の陵墓発見 中国河南省、遺骨も出土 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/world/china/091227/chn0912271936001-n1.htm
三国時代「曹操の墓」発見か、カギとなる石牌を確認―河南省 [サーチナ]
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1227&f=national_1227_019.shtml
曹操(永寿元年(155年) - 建安25年1月23日(220年3月15日)
字は孟徳、幼名は阿瞞また吉利。
沛国 ショウ(言偏に焦)県(現在の河南省永城市)の人。
中常侍・大長秋「曹騰」の養子「曹嵩」の子。
武将、政治家、詩人、兵法家。
後漢・献帝の丞相・魏王。
建安25年(220年)病死。
死後、息子の曹丕が後漢の献帝から禅譲を受け皇帝となると、太祖武帝と追号された。
(廟号は太祖、謚号は武皇帝)
後世では魏武帝、魏武とも呼ばれる。
スライディングパズルの一種「箱入り娘(日本での名称)」を中国では「華容道」といい
日本のモノで「娘」にあたる板(これを外に出せればクリア)は「曹操」。
「娘」を妨害する役割の板には「関羽」「張飛」「超雲」「馬超」「黄忠」のいわゆる蜀の五虎将と、
兵卒などが書かれて(描かれて)いる。
これは、
「赤壁の戦いで孫権・劉備軍に敗れた曹操が退却時に通ろうとしていた華容道には、劉備軍の伏兵(関羽)がいた!」
というあのシーンをモチーフにしたモノ。
http://sankei.jp.msn.com/world/china/091227/chn0912271936001-n1.htm
陵墓からは60歳前後とみられる男性の遺骨が見つかり、専門家による暫定的な鑑定結果によると、60代で死亡した曹操本人のものだという。曹操の陵墓の所在地をめぐっては諸説あり、これまで特定されていなかった。今回の発見で、曹操に関する謎が解明されるのではと期待されている。
三国時代「曹操の墓」発見か、カギとなる石牌を確認―河南省 [サーチナ]
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1227&f=national_1227_019.shtml
27日付中国新聞社電によると、河南省安陽市安陽県の安豊郷西高穴村でこのほど出土した1群の文字をしるした石牌に、「魏武王」などの銘文が刻まれていることが確認された。
「魏武王」は三国時代に活躍した曹操(155−220年)を指す。専門家によると、出土した石牌の文字はその場にある墓に葬られた人物を特定するための「カギ」となる。中国では各メディアが一斉に「曹操の墓を発見か」などと報じた。
曹操(永寿元年(155年) - 建安25年1月23日(220年3月15日)
字は孟徳、幼名は阿瞞また吉利。
沛国 ショウ(言偏に焦)県(現在の河南省永城市)の人。
中常侍・大長秋「曹騰」の養子「曹嵩」の子。
武将、政治家、詩人、兵法家。
後漢・献帝の丞相・魏王。
建安25年(220年)病死。
死後、息子の曹丕が後漢の献帝から禅譲を受け皇帝となると、太祖武帝と追号された。
(廟号は太祖、謚号は武皇帝)
後世では魏武帝、魏武とも呼ばれる。
スライディングパズルの一種「箱入り娘(日本での名称)」を中国では「華容道」といい
日本のモノで「娘」にあたる板(これを外に出せればクリア)は「曹操」。
「娘」を妨害する役割の板には「関羽」「張飛」「超雲」「馬超」「黄忠」のいわゆる蜀の五虎将と、
兵卒などが書かれて(描かれて)いる。
これは、
「赤壁の戦いで孫権・劉備軍に敗れた曹操が退却時に通ろうとしていた華容道には、劉備軍の伏兵(関羽)がいた!」
というあのシーンをモチーフにしたモノ。
メモ程度の記述。
鵜呑みにしないこと。
最初に日本語訳され(かけ)た聖書は日本語の音をローマ字で書いたものだったらしい。
江戸時代には知識人たちによって、漢籍の聖書などを参考にした部分的な日本語訳が行われていた模様。
(もちろん、禁教だったので他の漢文の書物に紛れさせてこっそりと)
幕末にギュツラフがヨハネ書などを訳した際にも中国語の聖書を参考にしていた。(『約翰福音之伝:ヨハネ福音の伝』)
ただし、本文は全文カタカナ。
開国後しばらくは、日本人は漢文を読み下せるじゃないか、ということで、中国語聖書を流用。
漢文読めない人もいるジャン、ってことでジョナサン・ゴーブルさんが全文かなで書き下した『摩太福音書(マタイ福音書)』を出版。
琉球で布教(禁教だったけど)していたバーナード・ジャン・ベッテルハイムさんは漢字仮名交じりの新約聖書を出版。
明治初期の日本伝道で活用されたものの、ウチナー口混じりだったため、内地の日本人には合わないと判断され、それほど普及せず。
明治に入って、ヘボン式ローマ字でおなじみのヘボンさんらが、イギリスの欽定訳聖書を参考に和漢混交の翻訳聖書を作製。(通称「明治元訳」)
大正時代に、欽定訳聖書が改訂になったのにあわせて、日本語訳聖書も改訂。(「大正改訳」)
明治訳・大正訳はおもにプロテスタントの宣教師さんたちが使用。(旧新約聖書―文語訳)
そのころカトリックはエミール・ラゲさんの私訳本の新約聖書を標準的に使用。(「ラゲ訳」)
また、正教会は当初漢訳聖書やプロテスタント刊行書を使っていたのだけれど、
宣教師さんがロシア系だったこともあって、用語やなんかがロシア語系(スラブ語)だったため、
プロテスタント用じゃ合わないってんで、独自の翻訳を模索。
1892年に『馬太伝聖福音(マタイ伝)』ができる。
1901年には新約部分の日本正教会翻訳が完成。
旧約部分は未だに全訳されていない。
この辺までがいわゆる「文語訳聖書」というやつ。
戦後「口語訳(聖書協会版)」がでる。(聖書 口語訳)
これは翻訳は確実だが、確実すぎて日本語的には奇妙なところが多く、
また、漢字を開きすぎて入れ、全体的な印象が「軽い」というか、
聖典っぽさが無い(荘厳さや格式の高さに欠ける)ということで不評。
作家の丸谷才一が「悪文の代表」といったとか言わないとか。
プロテスタントの牧師さんらもこの口語訳がお気に召さず、
1973年に『新改訳聖書』が出される。(聖書 新改訳)
カトリックサレジオ会のフェデリコ・バルバロさんが
ラゲ訳を元に新約の口語訳(バルバロ訳)を出したのが1957年。
旧約と合本されたのが1964年。(聖書―旧約・新約)
1987年にはカトリックとプロテスタントが合同で翻訳した「新共同訳」が出る。(聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき)
で、今一番で回っている聖書と言えば「新共同訳」ということらしい。
鵜呑みにしないこと。
最初に日本語訳され(かけ)た聖書は日本語の音をローマ字で書いたものだったらしい。
江戸時代には知識人たちによって、漢籍の聖書などを参考にした部分的な日本語訳が行われていた模様。
(もちろん、禁教だったので他の漢文の書物に紛れさせてこっそりと)
幕末にギュツラフがヨハネ書などを訳した際にも中国語の聖書を参考にしていた。(『約翰福音之伝:ヨハネ福音の伝』)
ただし、本文は全文カタカナ。
開国後しばらくは、日本人は漢文を読み下せるじゃないか、ということで、中国語聖書を流用。
漢文読めない人もいるジャン、ってことでジョナサン・ゴーブルさんが全文かなで書き下した『摩太福音書(マタイ福音書)』を出版。
琉球で布教(禁教だったけど)していたバーナード・ジャン・ベッテルハイムさんは漢字仮名交じりの新約聖書を出版。
明治初期の日本伝道で活用されたものの、ウチナー口混じりだったため、内地の日本人には合わないと判断され、それほど普及せず。
明治に入って、ヘボン式ローマ字でおなじみのヘボンさんらが、イギリスの欽定訳聖書を参考に和漢混交の翻訳聖書を作製。(通称「明治元訳」)
大正時代に、欽定訳聖書が改訂になったのにあわせて、日本語訳聖書も改訂。(「大正改訳」)
明治訳・大正訳はおもにプロテスタントの宣教師さんたちが使用。(旧新約聖書―文語訳)
そのころカトリックはエミール・ラゲさんの私訳本の新約聖書を標準的に使用。(「ラゲ訳」)
また、正教会は当初漢訳聖書やプロテスタント刊行書を使っていたのだけれど、
宣教師さんがロシア系だったこともあって、用語やなんかがロシア語系(スラブ語)だったため、
プロテスタント用じゃ合わないってんで、独自の翻訳を模索。
1892年に『馬太伝聖福音(マタイ伝)』ができる。
1901年には新約部分の日本正教会翻訳が完成。
旧約部分は未だに全訳されていない。
この辺までがいわゆる「文語訳聖書」というやつ。
戦後「口語訳(聖書協会版)」がでる。(聖書 口語訳)
これは翻訳は確実だが、確実すぎて日本語的には奇妙なところが多く、
また、漢字を開きすぎて入れ、全体的な印象が「軽い」というか、
聖典っぽさが無い(荘厳さや格式の高さに欠ける)ということで不評。
作家の丸谷才一が「悪文の代表」といったとか言わないとか。
プロテスタントの牧師さんらもこの口語訳がお気に召さず、
1973年に『新改訳聖書』が出される。(聖書 新改訳)
カトリックサレジオ会のフェデリコ・バルバロさんが
ラゲ訳を元に新約の口語訳(バルバロ訳)を出したのが1957年。
旧約と合本されたのが1964年。(聖書―旧約・新約)
1987年にはカトリックとプロテスタントが合同で翻訳した「新共同訳」が出る。(聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき)
で、今一番で回っている聖書と言えば「新共同訳」ということらしい。

戦国武将占い
四条 さやか (著), 霜月 かいり (イラスト), 茶屋町 勝呂 (イラスト), 櫻井しゅしゅしゅ (イラスト), K (イラスト), 尾張行 (イラスト), 柳矢 真呂 (イラスト), かざいエモ (イラスト), 暁 かおり (イラスト)
出版社: エンターブレイン (2009/10/9)
ほんとの自分が見えてくる! あなたは天下を取れる人?
【戦国武将占いとは?】
生まれた時期による性格傾向と行動パターンを分析し、統計的な要素を踏まえて作り出されたのがこの「戦国武将占い」。
地球は太陽の周りを360度回っているため、時期によりそれぞれの方角に見える天体は変わってきます。
この占いでは、東西の文献をもとに、生まれた時の天体の配置と性格傾向や行動パターンを分析。その分析結果と個性豊かな武将たちの特性を合わせた24タイプをもとに診断しています。
楽しみながらも役に立つ、人間関係の基本、人間関係UPのアドバイス、恋愛関係の基本、恋愛力UPのアドバイスを徹底掲載。
あなたの本来の性格である“気質”を知ることで、世界が変わって見えてくる!
いま、自分の誇りと命をかけて駆け抜けた武将たちが、あなたの生き方に問いかける!
【参加イラストレーター】
霜月かいり、茶屋町勝呂、櫻井しゅしゅしゅ、K、尾張行、柳矢真呂、かざいエモ、暁かおり

対決関ヶ原!戦国武将かるた
加来 耕三 (著), 岩元 辰郎 (イラスト)
出版社: ポプラ社 (2009/12)

戦国男子! Vol.1 (主婦と生活生活シリーズ)
企画・構成:榎本 秋
出版社: 主婦と生活社 (2009/07)
伊達政宗・真田幸村・長曾我部元親‥女子に人気の戦国武将だけを集めた、萌えエピソードでつづる美麗戦国絵巻

もっと知りたい 戦国武将ヒーローズ 戦国を駆け抜けた英傑伝説名将19選!!(DIA COLLECTION)
出版社: ダイアプレス (2009/7/13)
歴史に登場する戦国武将たちの中でも、とりわけ人気の高いのが“イケてる”と言われている人たちだ。
歴史を紐解いて、そのイケてる具合を探り出そうというのが本書の見どころでもある。
名将19人を選抜した、歴女のためのイケてる戦国武将ガイド!

戦国“漢(おとこ)”絵巻
学研 (編集)
出版社: 学習研究社 (2009/06)
描き下ろしイラスト満載で詳細解説。戦国武将プロフィールブック37人。
萌えるエピソード&4コマ掲載。
聖地巡礼のお供に、ゆかりの地紹介。
本格歴史ライターによる解説&甲胄作り収録。

限定品・戦国BASARA武将巡礼5冊セット【伊達政宗・真田幸村・長曾我部元親・上杉謙信・毛利元就】
戦国巡礼研究会 (著, 監修)
出版社: 株式会社JTBパブリッシング (2009/9/3)
「歴女」を中心とした歴史ファンの方々は、ゲームの世界を飛び出して、実際の武将が活躍した「ご当地」を巡礼することがブームになっています。
そんな歴史ファンの方々のための、戦国武将ゆかりの地を巡礼できるガイド本を5冊同時に創刊します!
歴史ブームの火付け役ともなった株式会社カプコンより発売されている話題のゲーム『戦国BASARA』のキャラクターを起用し、武将の生涯を時系列的にたどりながらファン必見の巡礼スポットを詳細にガイドします。
武将人気ランキング上位の「伊達政宗」「真田幸村」「長曾我部元親」「上杉謙信」「毛利元就」の5人をメインに取り上げ、そのほかにも「猿飛佐助」や「片倉小十郎」などの個性的な武将も紹介しており、戦国武将ファン必見の新シリーズです。
今回はネット限定で、戦国BASARA武将巡礼シリーズを専用オリジナル化粧箱に入れた、『限定品・戦国BASARA5冊セット』をご用意しました!戦国BASARAキャラクターをあしらった化粧箱はプレミアムものです!!是非お買い求め下さい。

戦国ファッション絵巻―戦国の魅力、いにしえのファッションで徹底解説! (マーブルブックス)
植田 裕子 (著), 山田 順子 (監修)
出版社: マーブルトロン (2009/08)
服がわかれば時代もわかる。
大人気・戦国時代のファッションサーチ。
その個性豊かなスタイルから、生き様も読み解いていきます。
威圧感バリバリ・戦国武将の鎧兜、武家のデイリーとフォーマル、女性のモード、パンクな傾奇者、庶民のストリートカジュアル、やっぱり気になる下着寝巻き事情、日常のヘアメイク…など、戦国ファンにはたまらないベスト・オブ・ベスト。
その他、戦国ファンにはたまらない「伊賀袴の作り方」「鎧の着方」などのユニークなコラムや、時代考証家・山田順子氏、『のぼうの城』『忍びの国』の大ヒット歴史小説家・和田竜氏のインタビューを掲載。
新しい世代の戦国ファンにおくる、 SENGOCK STYLE(センゴクスタイル)本が完成!です。

戦国ラブガイドブック
戦国武将研究会 (著)
出版社: 東京書籍 (2009/7/18)
厳選した戦国武将全29名にまつわる史跡で、この乱世を生きた男たちの熱きドラマを体感。
伝説の地、古戦場や終焉の地など、エピソードの残る場所、古戦場跡、祭り、関連グッズ、名言なども紹介した「戦国ラブ」なガイドブック。
憧れの戦国武将のゆかりの戦跡や神社、墓所、博物館などをめぐるために便利なガイドブック。
祭り、関連グッズの販売店などの情報も充実。
武将の人となりが見えてくる一冊。
| LOG | 2007 | 05 06 07 09 10 11 12 |
| 2008 | 01 05 06 08 09 10 11 12 | |
| 2009 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2010 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 | |
| 2011 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2013 | 01 02 03 04 06 07 08 10 11 | |
| 2014 | 02 05 06 08 12 | |
| 2015 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | |
| 2016 | 01 02 03 05 06 09 10 12 | |
| 2017 | 01 02 03 10 11 12 | |
| 2018 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 | |
| 2019 | 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 | |
| 2020 | 02 04 05 06 07 09 12 | |
| 2021 | 01 02 04 05 06 07 08 10 | |
| 2022 | 01 03 04 05 06 08 12 | |
| 2023 | 01 04 05 06 07 08 | |
| 2024 | 11 |
••• 日記内検索 •••
recent entries
••• calendar •••
••• Contact •••
••• Ranking •••
••• About Us •••
••• Amazon.jp •••
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
Thanks
••• thanks •••
Nicky!: diary CGI
Shi-dow: shi-painter
WonderCatStudio: dynamic palette
Promised Land: skin
非公式マニュアル : tips
賑町: icons
RSSアイコン:RSSicon
さくらインターネット :hosting
:hosting
Shi-dow: shi-painter
WonderCatStudio: dynamic palette
Promised Land: skin
非公式マニュアル : tips
賑町: icons
RSSアイコン:RSSicon
さくらインターネット
Caretaker Only